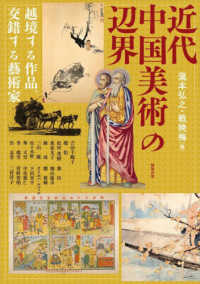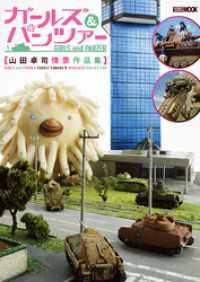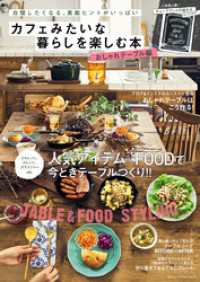内容説明
朝日新聞(読書欄)、読売新聞(「本よみうり堂」)、産経新聞(書評欄)、毎日新聞(「今週の本棚」)をはじめ、北國新聞、北日本新聞、東日本新聞、信濃毎日新聞など各紙で紹介! 第41回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞作品。 【本書の内容】ロシアの対外政策を、その特殊な主権観を分析しながら読み解く。今やロシアの勢力圏は旧ソ連諸国、中東、東アジア、そして北極圏へと張り巡らされているが、その狙いはどこにあるのか。北方領土問題のゆくえは。蜜月を迎える中露関係をどう読むか。ウクライナ、グルジア(ジョージア)、バルト三国など、旧ソ連諸国との戦略的関係は。中東政策にみるロシアの野望とは。ロシアの秩序観を知り、国際社会の新たな構図を理解するのに最適の書。北方領土の軍事的価値にも言及。第41回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞作品。