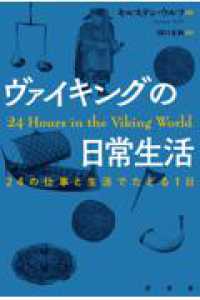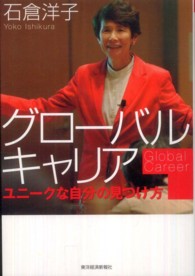- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
罵詈雑言が飛び交い、生産的な議論を行うことは不可能に思われる現在のインターネット。しかし、ネットの利用は本当に人々を分断しているのか? 10万人規模の実証調査で迫る、インターネットと現代社会の実態。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
43
多くの罵詈雑言が飛び交い生産的な議論は不可能に思えるインターネット。過激な書き込みを行っているのは一体誰なのか?何がネット上の議論を息苦しくしているのか?計量分析で迫るインターネットと現代社会の実態。社会を良くすると期待されていたインターネットは分極化の原因なのか。選択的接触などによる影響の可能性は認めつつも、豊富な統計から必ずしも直接的な要因にはなっていないことに着目し、過激なのは中高年を中心とするごく一部で、若者やサイレントマジョリティは意外とバランスを取っていることを指摘した内容は興味深かったです。2019/11/24
hatayan
37
SNSの普及により社会が分断されているとする俗説を検証。 ネットで左右両極端の主張が交わることなく荒れるのはごく少数の層が頻繁に書き込んでいるだけで、ネットが全体の世論を表すわけでは決してない。 異なる意見にアクセスするコストが紙や新聞に比べると劇的に低いネットの特性に若者は順応しており、左右を問わず情報を摂取。ものの見方をより柔軟で穏健なものとしている。 群衆の英知をもって世の中をよくしていこうとするネット草創期、Web2.0の頃の夢はまだ潰えていないことを力説する一冊です。2019/12/14
おさむ
36
世間に広く流布している、ネットによる社会分断説を10万人規模のネット調査によって覆す意欲作。ネットで分断はおきていないが、「起きているように見える」というのが結論。つまり真の社会分布の一部分だけがネット上には見えているのだという。過度な書き込みをするヘビーライターの存在とその閲覧頻度、一方のサイレントマジョリティーの萎縮効果に起因する、という。なるほど言われてみると、この逆説は説得力がある。でも、じゃあネットを真の社会と同じように見えるようにするにはどうすれば良いのか?という問いが残り、やや消化不良気味。2020/01/10
レモン
32
ネットで散見される極端な意見が分断を加速させているように見えるが、実際はそうではないということを調査し、証明されている。ネット利用により大半の人々は過激になるどころか、むしろ穏健化している。新聞やテレビの方がネットより偏った意見ばかりを収集しがちになる傾向があることには少し驚いた。声の大きい過激な少数派の意見には、極端に反応せずスルーに限る。2024/05/05
hk
25
■趣旨■ネットで分断ができたのではない。ネットで分断が発見されたのだ。 ■感想など■統計データを縦横に駆使して「ネットが社会の分断を増長させている」という俗説に挑んでいる。「ネット利用で社会分断が生まれるのならば、ネット利用頻度が多い若年層に分断が強くなるはずだ。だが分断が強いのは中高齢層である。このネジレは如何に?」「ネットは異論に触れる機会を増やすため、人々の政治的スタンスを穏健化させる。ネットリテラシーの高い若年層ほど分断が少ないのはその証左ではないか」といった新たな視座を得られた。有難しである。2020/02/06
-
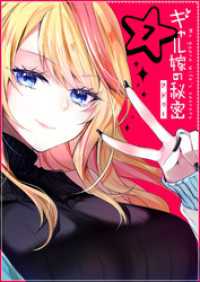
- 電子書籍
- ギャル嫁の秘密【単話版】(7) GAN…
-
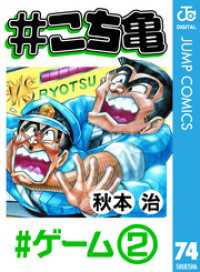
- 電子書籍
- #こち亀 74 #ゲーム‐2 ジャンプ…