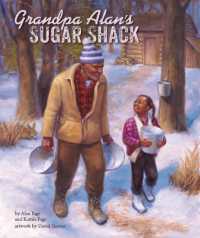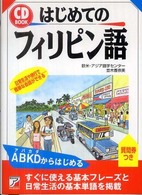内容説明
映画、ゲーム、アニメ、PV、アート、CG、マンガ……
本書が初の著書となる石岡良治がその博覧強記ぶりを存分に発揮し、ハイカルチャー/ポップカルチャーの枠組みを超えて視覚文化を語る!
写真や映画の発明とともに大きく変貌した近代から、デジタル画像や動画に至るまで様々な「視覚イメージの記録可能性」が増大し続けている。制作や操作も身近になって、視覚文化そのものが大きな変貌を遂げている。本書は、ありえないほど情報過多な現代の状況を踏まえ、個別領域の知の体系的な密度より、時代と対象領域の広がりと歴史性を重視し、分野間の横断性を強く意識した構成となっている。消費社会における様々な「カルチャー」としての視覚文化を分析することを目指すため「視覚文化」をあえて輪郭を曖昧にすることで考察しようとする。
現代の視覚文化を捉えるには、複数の速度、複数の歴史を「アクセルとブレーキ」ではなく「ギアチェンジ」していくモデルが求められるのではないか、と石岡は言う。わたしたちは消費ではないかたちで視覚文化とつき合うことは可能だろうか。文化のめまぐるしい速度変化にどのように対応すればよいのか?
動画以降の世紀を生きるための、ポピュラー文化のタイム・トラベル。石岡の圧倒的な知識を支える巻末の参考文献リストも圧巻!
「文化の民主化」が徹底されつつある今、まさに必読の書が現れた。
── 國分功一郎(巻末特別対談より)
伝説の男が、「日本最強の自宅警備員」と呼ばれるあの男がついにその重い腰を上げた……!
本書をもって世界は知ることになるだろう、本物の知性と本物の情熱の存在を。そして、石岡良治氏だけが両者をあわせもつことを。
── 宇野常寛
万事に賛否両方の論を用意して丁寧に論じていく、多分著者の身についたバランス感覚で、知らない人間を置き去りに自分の好みばかりに熱中して語る「サブカル」論者に通有の一人よがりとは無縁。さわやかだ。
── 高山宏
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
しゅん
サイバーパンツ
鳩羽
Ecriture
-
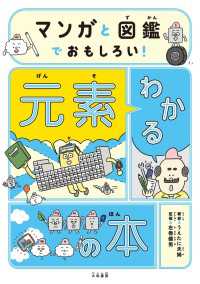
- 電子書籍
- マンガと図鑑でおもしろい! わかる元素…
-
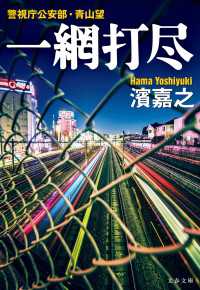
- 電子書籍
- 一網打尽 警視庁公安部・青山望 文春文庫