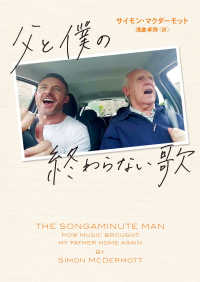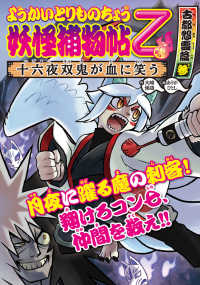内容説明
人工頭脳、原子力の開発、人工衛星など自然科学の発展はめざましい。しかし同時にその将来のありかたについて論議がまき起っている。著者は、自然科学の本質と方法を分析し、今日の科学によって解ける問題と解けない問題とを明らかにし、自然の深さと科学の限界を知ってこそ次の新しい分野を開拓できると説く。深い思索の明晰な展開。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おつまみ
60
科学とは何かが書かれている本。測定の本質や誤差の定義など、理系の人が見ても、かなり納得できる本になっている。2019/10/23
zirou1984
37
中谷宇吉郎と言えば『雪』が有名だけど、もしかしたらそれ以上に面白いと思える科学論入門書。中谷さんは科学を人間と自然との共同作業だと考えており、自然科学といえども自然の全てを知るべき学問ではないとその限界をきちんと見定めた上で、解ける問題をいかに観測し、理論化していくかについて話を進めていく。中でも数学についてが興味深く、「数学は人類の共有資産であり、個人の頭脳では到達し得られない所まで人間の思考を導いてくれるもの」という視点は目から鱗だった。こんなにも科学を人間的に感じられた経験は、他にないと言っていい。2013/12/20
なる
34
世界で初の人工雪を作り出した科学者の中谷宇吉郎による科学の本、ということで科学の可能性についてを言及している本、だと勝手に予想しながら読みはじめたら、冒頭から「科学には限界がある」といういきなりの直球を投げつけてくる。科学になんでも期待するのではなく、どうあっても解析することのできない自然現象の中から人間が認識できる法則を見つけ出して研究するのが科学である、という、かなり俯瞰した考えの内容で理系でなくてもわかりやすい。測定についてかなりスペースを割いているのが面白い。仕事柄こういうのしっくりくるので。2023/05/19
おせきはん
30
科学の本質を、わかりやすい言葉で論じています。新しい発見があっても全てがわかるわけではなく、科学にも限界があるとする謙虚さを忘れず、それでも再現可能な法則を追い求める姿勢は大切だと思います。2021/11/21
白義
26
見たものしか信じない、というような話はよくあるが、科学というのは見たものだけではなく、見えないもの、見たことがないものまでどう知っていくかという学問だ。再現可能、反復可能な実験といっても、自然界にはまだまだ再現困難なことも多ければ、再現しても完全に純粋な同一性を確保できないことも多い。それでも科学が普遍的な法則を探り当てるというのはどういうことなのか。人間にとって科学はいかなる意義と限界を持つのか。それを平易な言葉で、しかし並み居る科学哲学書より深いとこまで語った科学論の古典。60年前とは信じられない一冊2018/07/26