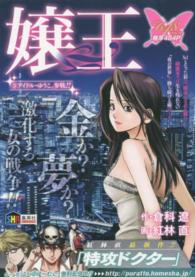内容説明
「愛国」が「反日」と結びつく不可解な国・中国。この構造は近世史・近代史の過程で形づくられた。1919年、北京の学生運動を皮切りに広がった五四運動は、現代に続くその出発点である。満洲事変をへて日中戦争へ向かうなかで、反日運動は「抗日戦争」と名を変えて最高潮に達した。本書は、日本・中国の近世史・近代史を政治・外交・経済・社会・思想にわたる全体史として描きだすことで、「反日」の原風景を復元し、ナショナリズムの核心にある「反日」感情の構造を解き明かす。古代から現代までの日中関係を俯瞰する論考を増補した決定版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
73
反日の源流は近代における日清戦争以降、第二次大戦終結にに至る間にあった日中間の戦争と理解していた。しかし、著者は相互理解が難しい根本が近世に遡る両国の社会構造の違い、特に中国の特異な統治構造から生じてると論じ、清朝の政治形態、社会と経済について、詳しくかつ平明に解説している。少数民族の満州族が圧倒的な人口の漢族を支配するに当たって、庶民の生活には関与せず、税だけ徴収できれば良しとした。皇帝・中央官僚・地方官僚と続く統治の上部構造は庶民には直接届いておらず、中間層が存在。税さえも庶民は徴税請負人に収めた。⇒2025/11/04
skunk_c
70
原著が書かれた2011年の6年前の反日デモから始まるのでこの書名となっているが、その内容はおおよそ17世紀~19世紀(近世~近代)の日中を対比したそれぞれの政治・経済・社会・外交史であり、この著者らしいコンパクトながら要点を押さえた内容。日本に対する人口規模10倍の中国(清)が17世紀に大人口増するが、この時生産が限界点に達して社会困窮を招いた。なんとこのことをマルサスより早く予測した人物が彼の地にいたという話には驚いた。西洋の衝撃に対する日中の対応の違いも端的。増補の講演録が読みやすくこれだけで満足だ。2025/10/26
さとうしん
12
本論では明清と江戸時代以来の日中の社会・統治構造の違いが近代化の過程や相互理解に影響を及ぼしたこと、中国が近代化を志したタイミングで日本がそれに逆行する対応を行ったことが双方の関係を抜き差しならぬものに追い込んだことを概観する。補論では、中国が一体であると主張したがるのは逆に中国が多元的であることを示しており、反対に日本は一元的であるので、中国蔑視となると官民こぞってという状態になってしまうという意見が面白い。2019/06/16
ピオリーヌ
6
まず増補以前の版を読んだ際の感想を。 現代の日中関係(しばしば反日と呼ばれる)が、清末期からのものでは無く、ひいては明時代からの相互認識の結果であるとわかりやすく書いてある。また、江戸時代日本と清時代中国が、近代化への過程の中で何故異なる道筋を辿ったかを経済史の視点から説いた点には目から鱗であった。お勧め。 →補論は筆者が講演で話した「日中関係を考える」が追記されている。日本は一元的、中国は多元的。2019/12/23
Hatann
5
中国における「反日」の深層構造を探る。現代中国の理解のため歴史を学ぶには15世紀以降で足り、近世に遡って中国・日本の相違を素描する。中国と日本との違いが明確になるのが15世紀以降である。中国は日本と異なり、官民の乖離が甚だしく、政治と経済の乖離も大きい。北方と南方がバラバラで多民族社会を形成している。貿易を通じて両地域の関係が深まる一方で、これらの相違から生じる矛盾が「倭寇」として現れた。政冷経熱の根源的な構造が以降も「反日」として現れることが示唆され、官民の乖離の小さい日本では違和感を覚えることとなる。2019/07/14
-
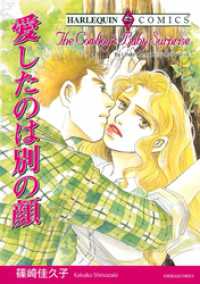
- 電子書籍
- 愛したのは別の顔【分冊】 5巻 ハーレ…
-
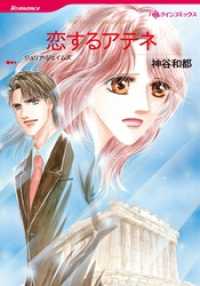
- 電子書籍
- 恋するアテネ【分冊】 6巻 ハーレクイ…
-
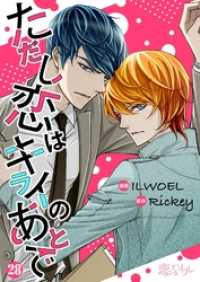
- 電子書籍
- ただし恋はキライのあとで(フルカラー)…
-
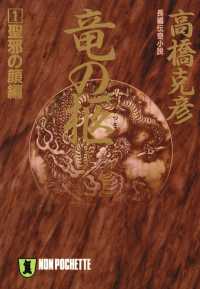
- 電子書籍
- 竜の柩(1)聖邪の顔編 祥伝社文庫