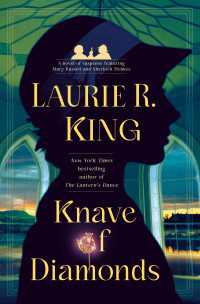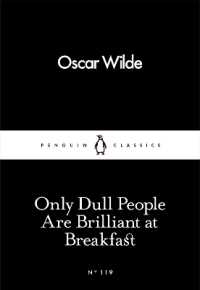内容説明
弥生時代がぐっと身近になる一冊 弥生時代と聞いて、皆さんはどんなものを思い浮かべますか? 渡来人、稲作、絵柄のないつるりとした土器、環濠集落、卑弥呼と邪馬台国、続縄文文化に貝塚文化…… 学校で習ってなんとなく聞いたことがある時代だからこそ、いろいろなものが思い浮かぶと思います。 では、実際のところ、弥生人たちはどのように日々を暮らしていたのでしょうか? この本は研究から見えてきた弥生の姿を、小難しいことを抜きにしてザックリ知るための入門書です。 想像も交えながら、弥生時代の暮らしを見に行きましょう!
目次
●彼らに会いに行く前に知っておきたい弥生知識
基本のキ
弥生人はどこから来たの?
弥生人の身体測定
弥生人のルックス
・Column:弥生時代の恋
●1章● 社会の移り変わり
列島に異なる文化が存在した時代
コメの美味さに激震走る!?
大陸とのおつき合い
鉄器に魅了された弥生人
環濠の中はとっても安心!?
皆でムラを守れ!
争いのはじまり
壮絶な争いの痕跡
支配するもの、されるもの
・Column:隣の芝生は青かった!?
●2章● 衣食住とお仕事
弥生人の普段着
土器からわかるユニークな風習
・Column:縄文人と弥生人 顔の違い
弥生人はコメ至上主義?
グルメな弥生人
コメの炊き方いろいろ
弥生のコメはどんなコメ?
住居は円から四角へ
世帯事情あれこれ
移り変わるお墓のスタイル
弥生のイチオシ便利グッズ[農耕編]
弥生のイチオシ便利グッズ[織物編]
弥生のイチオシ便利グッズ[技能編]
・Column:米作りをやめた人々
●3章● 弥生時代の祭祀
弥生人の祈り
祈りを司るシャーマン
バラエティ豊かな祭祀の道具
・Column:消えた土偶のナゾ!?
絵から読み解く弥生の世界観
・Column:これって何? 銅鐸モチーフクイズ
●4章● 弥生遺跡ガイド
はじめての弥生遺跡探訪
吉野ヶ里遺跡
須玖岡本遺跡
板付遺跡
土井ヶ浜遺跡
荒神谷遺跡
妻木晩田遺跡
青谷上寺地遺跡
池上曽根遺跡
大阪府立弥生文化博物館
・Column:「魏志倭人伝」は正式名称ではありません
●5章● 続縄文時代と貝塚時代
続縄文時代とは
続縄文時代の遺物
貝塚時代とは
貝塚時代後期の遺物
・Column:貝塚時代後期のお洒落アイテム「貝符」
●6章● 卑弥呼と邪馬台国の謎
卑弥呼ってどんな人?
卑弥呼の住まい
卑弥呼の食卓
邪馬台国はどこにある?
・Column:日本は弥生時代 その頃、世界では…
とってもカラフル!弥生時代の小さくてかわいいもの
・Column:弥生時代のイヌとネコ
弥生土器あれこれ
弥生土器の形
エピローグ 弥生から古墳へ
弥生時代の主要な遺跡/写真提供・取材協力一覧
参考・引用文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
美登利
きみたけ
ダミアン4号
南北
えんちゃん