内容説明
従来のソフトウェア開発とは、「既に正解があり、記述された正解をそのまま形にする」というものづくりであり、いかに効率よく作るかという観点が主眼でした。そのため、正解の見えないなかで手探りで進んでいくことが必要となる不確実性の高い現代においては、うまく噛み合わない状況になっている開発現場も少なくありません。
本書では、共創を実現する具体的な手段としてのアジャイル開発を下敷きに、これからのソフトウェア開発/デジタルプロダクトづくりに、作り手(エンジニア、開発者、デザイナーなど)と、それを必要とする人(クライアント)がどのように臨むべきなのか、その考え方と行い方を具体的に提示する一冊です。
「正しいものを正しく作る(著者の掲げる理念)」とは、すなわち「正しくないものを作らない」戦略をとることであり、そのためには粘り強く「正しく作れているか?」と問いに置き換えながら探索的に作っていく必要があります。問いを立て、仮説を立て、チームととともに越境しながら前進していく。本書はそのための力強い手引きとなるでしょう。
目次
イントロダクション 正しいものを正しく作れているか?
第1章 なぜプロダクトづくりがうまくいかないのか
1-1 なぜ、プロダクトづくりに苦戦し続けるのか?
1-2 多様性がプロダクトの不確実性を高める
1-3 不確実性とのこれまでの戦い方
1-4 アジャイル開発への期待と失望
第2章 プロダクトをアジャイルにつくる
2-1 アジャイル開発とは何か
2-2 スクラムとは何か
2-3 スクラムチーム
2-4 スクラムイベント
2-5 スクラムの成果物
2-6 自分たちのアジャイル開発とどう向き合うべきか
第3章 不確実性への適応
3-1 アジャイル開発で乗り越えられない不確実性
3-2 共通の軸を持つ
3-3 余白の戦略
3-4 スプリント強度を高める戦術
3-5 全体への共通理解を統べる作戦
第4章 アジャイル開発は2度失敗する
4-1 チームは2度、壁にぶつかる
4-2 プロダクトオーナーの果たすべき役割
4-3 チームとプロダクトオーナー間に横たわる2つの境界
第5章 仮説検証型アジャイル開発
5-1 自分たちの基準を作る
5-2 正しくないものを作らないための原則
5-3 仮説検証型アジャイル開発における価値探索
5-4 1回目のモデル化(仮説キャンバス)
5-5 1回目の検証(ユーザーインタビュー)
5-6 2回目のモデル化(ユーザー行動フローのモデル化)
5-7 2回目の検証(プロトタイプによる検証)
5-8 その他の検証手段
5-9 仮説検証の補足―本質、実体、形態
第6章 ともにつくる
6-1 正しいものを正しく作る
6-2 視座、視野を越境する
6-3 チームとともに作る
あとがき
参考文献/索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
むらさき
めかぶこんぶ
kumokumot
izw
-

- 電子書籍
- 黒影のジャンク~大決闘会編~(27) …
-

- 電子書籍
- 両極の少年【タテヨミ】第163話 pi…
-
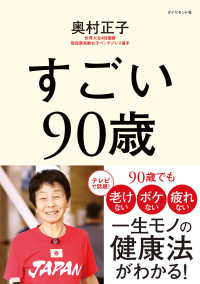
- 電子書籍
- すごい90歳
-
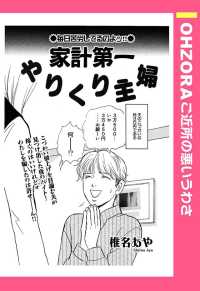
- 電子書籍
- 家計第一やりくり主婦 【単話売】 - …
-
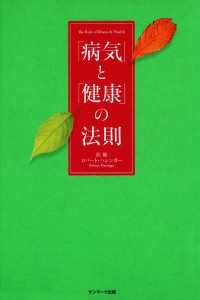
- 電子書籍
- 「病気」と「健康」の法則




