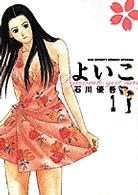内容説明
自己と文化を解放するための〈科学の寓話〉。オーストラリア・レッドロックのアボリジニーに伝わる「虹の蛇」の神話、カトマンズ盆地・「虹の立つ村」のマヤ・クマリの千里眼、そしてラマ僧の語る虹を中心とした世界の成り立ち―意識と物質の発生をイメージさせる虹の体験は、両義性という終わりなき解釈のらせん階段から自己と文化を解き放つ「野性的な科学」へと我々を誘う。メタフィジカルな八つの物語が紡ぎだす新しい世界。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りー
32
大地のエネルギーの迸りとしての「虹」やインドネシアの呪術士に関するあれこれを書き記した、小説の様でいて手記やエッセイの類いと見せかけ、哲学書でもあり文化人類学的な書物でもある一冊。読んでいるその瞬間は「あ、なるほどね!」と思うものの、どういう内容だったのか後になって思い返してみるとぼんやりとしか掴めていない。あまりに広範な知識を求められる上に専門用語が無数に出てくるので一読では理解出来なかった。しかし呪術士の思考体系はたいへん興味深く、我々がお金を払って電車に乗る事なんかも呪術と似た行為なのかもしれない。2014/06/03
yumiha
28
「虹」と言えば、これまで「架け橋」だの「はかなく美しい」だのというイメージしかもっていなかった。アボリジニーの言い伝えによれば、虹の足元には蛇がいてその身体から虹が作り出されるのだという。大地の生命力の象徴でもあり、また病気の起源などのまがまがしいものでもあるという。なぜか日本でも、中世の古文書には、蛇が大空に向かって駆け上ると虹が現れると書かれているそうな。これからは虹を見たら、蛇の姿を想像してしまいそうだ。でも、宗教も哲学も苦手なので、詳しい教義も理論もほとんど理解できないまま終わった。2017/02/06
ロータス
2
虹と蛇、石と市といった様々なイメージが頭の中で瞬時に現れる不思議な文章。小説のようで小説でなく、批評のようで批評でない、たぶんジャンル分けを拒んで選ばれた文体なのだろう。ただ『チベットのモーツァルト』からの神秘主義思想にはだんだんついていけなくなってきた。「虹の理論」「虹の理論2」以外では「エリアーデのために」がタントラの性の秘儀について真面目に説明されていて面白かった。2022/03/27
ANT
1
この本は、哲学書でも宗教学書でも文化人類学でも小説でも詩でもないが、同時にどれでもあるという特異な作品だ。学者とは思えない詩的センスを感じるだけでも一読の価値はある。インドネシアのバリアンと呼ばれるメディスンマンと、ブラックマジシャンとの対立を描いた「ファルマコスの島」は完全にSFだし、「エリアーデのために」にあるチベットや中国の房中術のブッ飛び具合に驚かせれるし、ダンテが神曲に至る過程を綴った「ハッピー・エンド」は愛の科学だ。(続く)2010/03/29