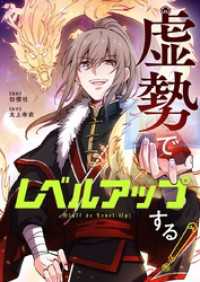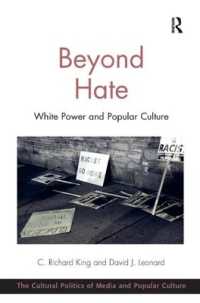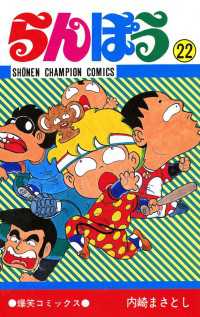内容説明
「はい、次の質問」。露骨な圧力、質問妨害、時間削減──閣僚はじめ政治家の会見で何が起こっているのか。政治部記者として歴代官房長官を500回以上取材した著者が、「もう自由に質問できない」この国の今に警鐘を鳴らす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
181
菅官房長官と、東京新聞社会部・望月衣塑子(いそこ)記者のバトルを詳しく知りたくて第2章「全詳報」を真っ先に読んだ。が、ますます、政治不信と新聞記者の質の低下がはっきりし、失望感が増してしまった。東京新聞は名古屋に本社があるブロック紙「中日新聞」の子会社で、望月記者は政治部でなく社会部所属の「異色」の記者。この事実は、興味深かったが、だからどうした、日本が「質問のできない国」になってしまった、と嘆く前にもっと重要なことは身近にある気がする。2019/08/05
kinkin
94
記者会見の場で記者の質問に対して「あなたに答える必要はありません」この記者会見の様子はニュースで見ていた。この日本という国で国民の知る権利がどんどん侵されていることに気づかなければならない。森友や加計問題では大掛かりな資料の隠蔽や捏造が行われてもそれがまかり通ってしまう国。国民に対する丁寧な説明どころかその説明さえなくなってきている。本書p122 記者には質問を制限し、見せたくないものは法を変えてでも見せない。私達の「見る」「聞く」を封じることが進んでいます。と書かれている。国民は怒らねば。2019/08/07
fwhd8325
57
著作というのはある意味書き手の都合いい面を強調してるかもしれないけれど、断片的に知る情報は、ここに書かれていることと相違ありません。今、私たちの国はどこへ向かおうとしているのか、最近は特にそんな不安が強くなってきています。歴史は繰り返すではないけれど、けっして起きてはいけない歴史があったことを忘れてはいけません。あの歴史の前夜、私たちの国は様々な権力による統制が行われていました。声を上げられる国でなければいけないんです。2019/09/25
おさむ
41
東京新聞の望月記者を描いた映画にも登場していた朝日新聞の南記者の新書。彼女を援護射撃してきた経緯に併せて、安倍政権がいかに嘘やデタラメを繰り返しているかをファクトに基づいて紹介している。不祥事慣れでもう変だと感じなくなっていることに愕然とする。それでも空恐ろしく感じたのは最高裁判事が全て安倍政権の任命になり、日弁連の推薦者が選ばれなくなったこと。米国のトランプ大統領にも似た人事による司法統制の動きだ。ますます報道統制・コントロールが巧みになる政権にいかに抗うのか。今こそメディアの底力が問われていると思う。2020/01/31
TATA
27
知り合いから譲り受けたので一読。ネット社会の進展に伴い、メディアも政権から選別される時代になったということ。この点にフォーカスすれば論点はより明確になっただろうと考える。2020/09/24