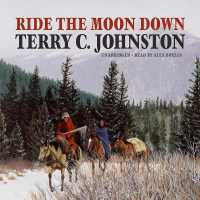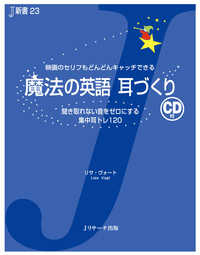内容説明
自民党は結党以来38年間にわたり政権を担い、2度「下野」したが、2012年に政権に復帰。一強状態にある。その間、自民党は大きな変貌を遂げた。本書は、関係者へのインタビューや数量的なデータなどを駆使し、派閥、総裁選挙、ポスト配分、政策決定プロセス、国政選挙、友好団体、地方組織、個人後援会、理念といった多様な視角から、包括的に分析。政権復帰後の自民党の特異な強さと脆さを徹底的に明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
31
時系列的な、また、空間的な幅を含む、現在の自民党がよくわかる本だった。自民党は長年の政権党であるため、そのまま、日本の政治がよくわかる本ということでもある。こういう本が読みたかった。専門家が書いた本格的な政治入門書とも言えるが、基本的な理解を通じてこそ、世の中に現れてくるトピックスの正しい座標を把握することができる。2001年の総裁選挙で「古い自民党をぶっ壊す」と叫んだ小泉首相は、本当に自民党をぶっ壊して2009年に政権を失うことにつながったこと、現在の安倍首相の手腕など、読みどころも多い読書となった。2018/03/09
ぐうぐう
30
選挙の度に選択肢がないのを嘆くことにも、最近ではなんだか慣れてきた。魅力的な野党の不在は無党派層を増大させ、結果として自民一強を継続させる。しかし本書を読むと、棚ぼた式に自民党が与党の座に君臨できているわけではないことがわかってくる。派閥、総裁選、ポスト配分、政策決定プロセス、国政選挙、友好団体、地方組織と個人後援会等々、多角的な視点で自民党を包括的に分析する本書から見えてくるのは、自民党という政党の決定的なしたたかさだ。ひとことで言えば、権力をとことん理解している、ゆえに自民党は強いのだ。(つづく)2017/06/30
Piichan
22
自民党の基礎知識を学ぶにはよい本だと思いました。2009年総選挙で下野しても短期間のうちに政権復帰できたのは地方組織の強さが大きいというのは私も感じていました。自民党は自営業者の支持が厚く、彼らは世襲することが多いため地方の支持基盤が強固になりやすいというのはなるほどと思いました。日本共産党も地方政治が強いので安定しています。立憲民主党が注目されていますが、総選挙後の課題は地方組織の整備でしょう。民主党、民進党は大都市の無党派層を支持基盤にしてきたためか風頼りの選挙になりがちだったわけですし。2017/10/06
あんころもち
19
最初に知った首相が小泉純一郎であろう僕らの世代にとって、日本政治がその前はどうだったか、その後はどうなったかを知るのに最適な見取り図を与えてくれる一冊。 本書は、派閥、ポスト、政策決定、国政選挙、財界との関わり、地方組織でそれぞれ章立てして、それぞれにおいて総裁権力がどれほど強くなったか、一方で党そのものはそこまで強くなっていないことなど、小泉から安倍に至る大きな流れの中でデータを用いて新書にしてはかなり深く分析する。 久々に超おすすめの新書。2017/06/03
msykst
17
頻繁に言われる様に、かつての自民党政治の特徴は「(1)ボトムアップとコンセンサスを重視する意思決定」と、「(2)派閥政治によって生まれる党内の多様性」であり、これが利益誘導政治をもたらしてたと。それが94年の政治改革、小泉改革、民主党への政権交代等々の転換点を経て崩壊する過程と、それを経た安倍政権の政治手法を分析する感じかと。多分安倍の右翼っぽい感じとか金融政策の過激さとかってのは本人の信条に基づくものではなく、行きがかり上やらないといけない役割を引き受けている、という感じなんでしょうね。 2018/10/07
-
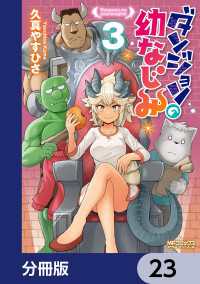
- 電子書籍
- ダンジョンの幼なじみ【分冊版】 23 …