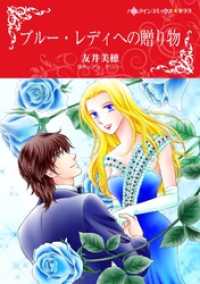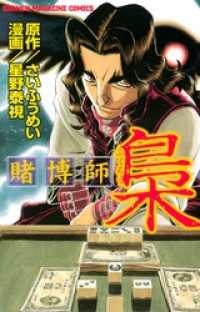内容説明
アインシュタイン、モーツァルト、ヴィトゲンシュタイン、南方熊楠、芥川龍之介……「異脳の人」を殺さないための処方箋を明かす!
本書は、「創造」「才能」がいったいどのようにして生まれてくるのかを、誰もが知る天才たちを具体的に挙げながら、精神医学的見地から解き明かす作品である。
歴史上の天才たちには、精神疾患の傾向がみられることが多い。これは数々の医学的データから明らかになっている。たとえば音楽の天才モーツァルトは、明らかに発達障害の特徴があった。落ち着きない動作、「空気」を読まない所作などで周囲から嫌がられた。一方、創作に入ると「過剰な集中力」を示し、素晴らしい作品を瞬く間に書き上げた。
物理学の歴史を変えたアインシュタインは、ASD(自閉症スペクトラム)の症状を示していた。他者とのコミュニケーションに障害を抱え、言葉の発達も遅れていた。しかし、飛び抜けた数理的洞察力によって、古典的物理学の常識を覆す理論を打ち立てた。
著者は、発達障害には「マインド・ワンダリング」(いわゆる「心ここにあらず」の状態)、そして「過剰な集中」という2つの特性があることを指摘。そして、相反するこの2つの特性が、天才の特異な能力と密接に結びついているという仮説を提示する。
そして、「才能をもつ子供や若者をいかに殺さずに育てるか?」というテーマについて、日本社会が取り組むべき解決策を提案する。発達障害に悩む親や本人にとっても福音となる作品だ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AICHAN
54
図書館本。発達障害とは何なのか知りたくてこの本を読んだ。自閉症もそのひとつだと知った。そして発達障害が何らかの天才的な才能を引き起こすことがあるという。万能の天才ダ・ビンチを例外として天才の多くが偏った才能を持つことには気づいていた。山下清がサヴァンというのには十分に納得できた。司馬遼太郎の『胡蝶の夢』に登場する島倉伊之助(司馬凌海)がASD(自閉症スペクトラム障害・アスペルガー症候群)というのは「なるほど」だった。芥川龍之介も夏目漱石も野口英世も大村益次郎もアインシュタインもモーツァルトも↓2020/06/19
Tomoichi
42
天才と精神疾患との関係を実際の人物や小説の登場人物など具体例で解説。一気に読ませる内容です。精神疾患と遺伝の関係や癲癇と天才との関係も欲しかった。最終章の「誰が大脳を殺すのか?」には同意できかねる意見も多い。日本が100年に一人の天才を望むのか一年に一人の秀才を望むのか国民合意ができなければ欧米型教育は難しい。しかし発達障害の子供達への支援と周囲の理解、親の協力はより必要になるだろう。2019/09/01
yapipi
39
芸術家、文豪、学者などの天才とされる著名人と発達障害との関係を広く論じた著作。発達障害の種類とその行動や心理の特徴、天才がそのどれに当たるのかが書かれている。たくさんの例が短く取り上げられているが、正直切り込み不足の感は免れない。著者が彼らを直接診断したのではなく、伝聞などを元にして書いているので仕方がないと思う。また、著者は芸術や文学などにそんなに共感してないと思われる。とは言っても、今後もっと深く知る手がかりになる本だと思う。☹️夢中になれる芸術のほとんどには病的な何かがあるのだな、改めてそう思う。2025/09/25
tomi
37
天才と呼ばれる人たちは発達障害や精神疾患と関りが深いという(実際に小説やドラマでも天才的な人物=変わり者に描かれることが多い)。芸術家や文豪、科学者といった多くの歴史上の有名人の症例を作品や評伝などから読み解き、診断している。うつ病や統合失調症の例もあり、発達障害から逸脱している感も受けるが、哲学者ヴィトゲンシュタインのように統合失調症と思われていたが実際はASDだったという例も少なくないようだ。2020/04/13
gtn
29
有名人の症例をふんだんに紹介しており、飽きない。ただ、統合失調症、薬物中毒、アルコール依存症等、本当に発達障害の事例なのかと首をかしげるものも多い。2019/11/23