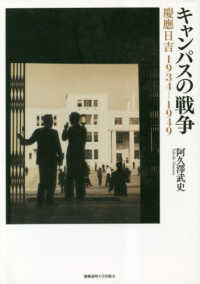内容説明
サメもヒトもアザラシも、生物はなぜこんなにも多様に進化したのか――その謎を解く鍵は「体温」にあった。気鋭の生物学者が世界各地でのフィールドワークを通し、壮大なメカニズムに迫る!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
49
2019年刊。小型の記録計を取り付ける手法を使い、ペンギン、サメ、アザラシなどの生態を調べる。著者の目的は、動物共通の法則を確かめる事。400年生きるニシオンデンザメから短命なミドリムシまで、重量と体温の二つをキーに見れば、単位あたりの代謝量は同じ。ゾウとネズミ、人間なら大人と子供の「時間感覚の違い」も、この法則で説明できる。半ば物理の問題だけど、丁寧な解説のお陰で一応理解できた。生き物好きではないのに極地まで赴き、サメやペンギンに抱きつく著者は、見上げた学者魂の持ち主。現地のよもやま話がとても面白かった2021/04/03
ころこ
41
何となく読んでみた本が自分の関心に近いところにありました。体の大きさと体温が決まればエネルギー消費量が決まり、それに応じて生活スタイルが決まり、成長速度が決まり、寿命が決まり、進化のスピードが決まる。生態学の代謝量理論だそうです。自然は多様性だというけれども、実は人間が認識する少数の原理によって成り立っていることを強調しています。実際に万事がそうだというのではなく、自然をありのままみることが出来そうな分野だからこそ、「視点の高度」という表現で、人間がそれをどうみるかにこだわる態度は非常に知的だと思います。2021/07/29
七月せら
24
恐竜の血は温かかったのか冷たかったのか。年をとるほどに時間の流れが加速して感じるのは何故なのか。そんな素朴で魅力的な疑問は、究極には「地球上には何故これだけ多くの大きさ、体温、寿命のバリエーションに富んだ生物が繁栄しているのか」という壮大なミステリーに通じている。人工衛星の視点から自然界を俯瞰し、例外だらけの動物の行動も物理の法則をもって解釈することで見えてくる、自然界を貫く法則。フィールドワークの体験談は冒険小説のように、難しい数式や法則の話は入門書よりなお分かりやすく、文句なしに面白い本でした。2019/08/22
もえたく
21
「年をとると時間の流れが早く感じる」のは、北極の深海で400年生きる巨大なニシオンデンザメの生態などの例に挙げ「代謝量の変化」で説明され、納得することしきり。過酷なフィールドワークの面白ハプニングと、バイオロギングによる最新の研究成果を織り交ぜながら、物理学も優しく解説してくれて読みやすい。こういう研究者が沢山出てくると、子供達も理科好きになると思いました。2020/02/15
tom
20
著者は、この本に書いたことを「体の大きさと体温さえ決まれば、コガネムシであれツキノワグマであれ、エネルギー消費量(代謝量)が決まる。代謝量が決まれば、生活スタイル、成長速度、寿命、進化のスピードが決まる。生命活動は化学反応の組み合わせ、どんな生物にも例外はない。」とまとめる。著者は、これをもとにして生態学の大統一理論を目指しているらしい。そのツールがバイオロギングによる生命活動の計測。そうなのか、著者の研究は、ここに向かっていたのかと、かなりの驚きを持って読む。面白い。2025/10/01
-

- 電子書籍
- 没落令嬢は社畜になった 第41話 柳家…
-
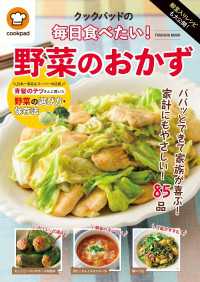
- 電子書籍
- 殿堂入りレシピも大公開! クックパッド…