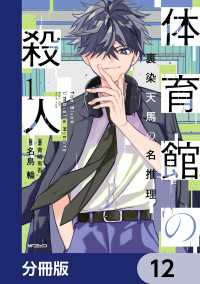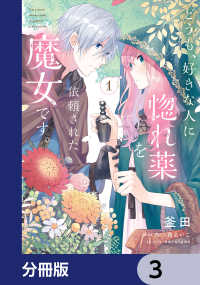- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
これまでの通史の多くは、国家としての日本が辿ってきた道筋を軸に記述してきた。それに対し本書は、人びとの動きがつくり出す一つの流れ――人間関係から社会の仕組みまで――を「システム」として捉え、その変遷を軸に近現代日本の歴史を叙述する。本書は、“幕末・維新―戦前編”として、システムA1(国民国家の形成)・システムA2(帝国主義への展開)とシステムB1(戦争への動員体制)を軸に、そのシステムのもとでの人びとの経験とその意味を考える。システムの推移を追うことで、さまざまな出来事が、その力学の中で作用し合っていることが見えてくる。“いま”を知るための手掛かりとなる近現代日本史の決定版。高校の新必修科目「歴史総合」にも対応! 【目次】はじめに/第一部 国民国家の形成/第一章 幕末・維新(一八五三―一八七七年)/第二章 民権と憲法(一八七七―一八九四年)/第二部 帝国主義への展開/第一章 日清・日露の時代(一八九四―一九一〇年)/第二章 デモクラシーと「改造」(一九〇五―一九三〇年)/第三部 恐慌と戦争/第一章 恐慌と事変(一九三〇年前後)/参考文献/略年表
目次
はじめに
第一部 国民国家の形成
第一章 幕末・維新(一八五三―一八七七年)
第二章 民権と憲法(一八七七―一八九四年)
第二部 帝国主義への展開
第一章 日清・日露の時代(一八九四―一九一〇年)
第二章 デモクラシーと「改造」(一九〇五―一九三〇年)
第三部 恐慌と戦争
第一章 恐慌と事変(一九三〇年前後)
参考文献
略年表
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
61
日本の近現代をAⅠ~CⅡの3期6つの「システム」と捉えて概観する試み。本巻はBⅠまで。AⅠ=国民国家、AⅡ=帝国主義との見立てで、AⅠが完成する前にAⅡに突入するという説明は、展開の速い日本近代史を上手く表している。分かりにくいのがBⅠで、どうやら大量生産・大量消費の成立と統制社会のようなのだが、続巻のBⅡを読まないとAⅡとの区別がつかめない。多くの先行研究を統合して、著者が再構築しており、政治・経済のみならず社会・文化・思想にまで配慮が届き、バランスの良い記述と思う。唯一弱いのが軍の動きかな。2021/06/06
もりやまたけよし
27
近現代史の通史として期待した。システムという言葉が出てくるたびに、訳が分かんなくなってしまう。システムというくだりを飛ばすと、全体の流れが分からなくなってしまい迷子になる。2020/09/26
かんがく
13
歴史を構造的に理解するのはあまり好きではないが、ここまで徹底的に構造化していると面白い。様々なテーマについて時代を追って綺麗に整理されているので流れの再確認には適切な一冊だった。2024/07/14
さとうしん
13
日本近現代史の展開をシステムの交替という視点から読み解く。前編となる今巻は幕末から1930年代までの国民国家の形成、帝国主義化の達成、全体主義化の過程を追う。「万歳」の誕生、文明化と衛生・不潔観との関係など、近代化と身体性を結びつける記述が印象的。2019/02/08
koke
10
普通に通史としても読めるが、大きなメタ歴史的主張をあえてしているところが大きな特徴。構造主義を思わせる「システム」という語により、あとから客観視して初めて分かるいくつかの歴史の深層を大胆に示す。本書はそれらの深層と諸々の出来事とを絶えず行き来するような記述となっている。私は通史を読むと知らない出来事の羅列に圧倒されてぼーっとなってしまうので(著者の捉え方が唯一絶対ではないとはいえ)これはありがたい。続編も楽しみ。2025/12/29