内容説明
世界遺産、京都の龍安寺に枯山水の名園がある。その名は石庭。十五の石が何を基準にしてレイアウトされ、また何をテーマにしたのか分からないため、「謎の庭」「推理の庭」「ミステリアスな庭」とも呼ばれる。数百年もの間、多くの識者がいろいろな推理を提唱してきた。虎の子渡し、七五三、満月、星座カシオペヤ、朱山五陵、扇、心の字、京都五山、楽譜、豊臣秀吉石狩り、黄金比、遠近法……。このうち最も有名なのは「虎の子渡し」だが、十五の石と四匹の虎(親・彪・子・子)がどんな関係にあるのか誰も説明できないため、それ自体が「日本の謎」と見なされてきた。けれども、問題を次のように書き替えることで、この難問がついに解き明かされた──。「虎の子渡しと呼ばれるからには、四匹の虎(=四つの石)は実際に川(=白砂)を渡ったに違いない。そもそも、川を渡る以前、十五の石はどのように配置されていたのか?」。このように「虎の子渡し」を一種の暗号と仮定して推理を進めると、その背後から「龍と虎」が一対になった壮大な庭が姿を現したのである。それと同時に、長年にわたって庭園・建築・デザイン関係者を悩ませてきた、「秘密のレイアウト」もようやく解明された。謎解きの道具になったのは、清少納言の名と結びついた「智恵の板」と、当時使われていたL字型の曲尺である。十五の石は、八つの曲尺三角形でつくられる「龍安寺智恵の板」に従って、レイアウトされていた。本書は新旧「五十五の推理」を集大成して、石庭の核心に迫った。なぜ五十五なのか。それは、「十五の石」と「五十五の推理」を組み合わせることによって、宇宙全体を表現できるからである。石庭の作者の鋭く激しく熱い知性は、現代知識人の水準を遙かに抜いていた。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
Norico
はなもんも
呑司 ゛クリケット“苅岡
ととむ
-
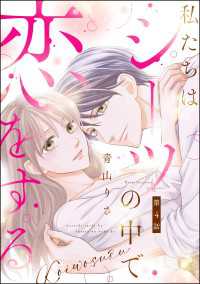
- 電子書籍
- 私たちはシーツの中で恋をする(分冊版)…
-
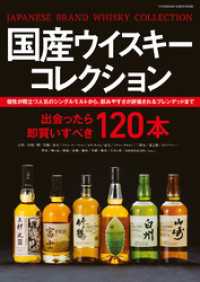
- 電子書籍
- 国産ウイスキー コレクション 双葉社ス…
-
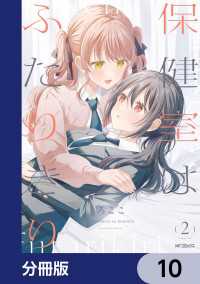
- 電子書籍
- 保健室はふたりきり【分冊版】 10 M…
-

- 電子書籍
- 会社をやめて馬主やります! ― アキコ…
-
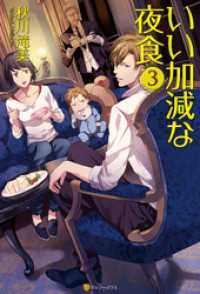
- 電子書籍
- いい加減な夜食3 アルファポリス




