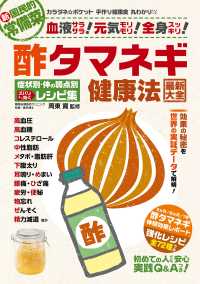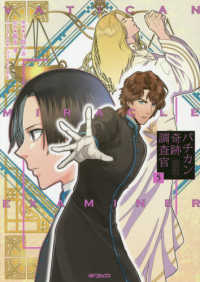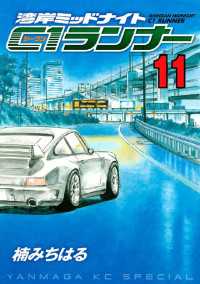- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人はいかにして「老い」や「死」と向き合うのか――。本書は、数多くの評論・エッセイを世に送り出してきた著者が、その晩年に自らの老いと重ね合わせ、したためたものである。市井に生きる無名の人間、友人、高僧、偉人……彼らの迷いや憂い、喜びや行動から学ぶべきヒントを提供する。「人生のゴールが薄っすらと見えて」きた時、その指針となる名著を、下重暁子氏の解説を添えて堂々復刊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SOHSA
20
《図書館本》生老病死はひとの定めでありかつゴータマ・シッダールタの出家する初因でもあったが、著者は老・病・死を改めて生の延長上に捉えることでどのように生きるかを淡々と述べている。著者ほどに未だ達観できない読み手は、時の流れに喘ぎ溺れながら必死に本書にしがみつこうとしていた。その手を緩めることだよと遠くから著者の声が聞こえた。なるほどそうか。執著を捨てること、手放すとはそういうことだったか。読後「ひとは生きてきたようにしか死なない」というタイトルが再び胸に刺さった。2023/03/21
大島ちかり
5
お勧めします。こんな本に出会えて良かった。 私の老い方の方向性を教えてくれました。 静かに泣きました。 今はくだらないことが多く惑わされていることを実感しました。先人に敬意を持って年長者に学びます。くだらないことはどうでもいい。 2020/03/05
めぐ
3
大正生まれの著者が老境に入り、シニア向けに人生とは老いるとは何であるかを古今東西のエピソードをあれこれと引用して語られた本。青年層が読んでもシニアの心意気や気概が伝わってはっとする所が多い。極寒のアラスカの地に棄老された2人のエスキモー老女が支え合い余生を豊かに全うすべく奮起し丁寧に日常を営んでいく話は、老人とはけして無力感と諦観に埋もれた人々ではなく、活力の涌泉を内包し、休止中の活火山の如く静かな日常を紡いでいるに過ぎない事に気付かされる2021/08/14
cocolate
1
この人の名前を「野村本」で観た時に何かで聞いたことあるなあと思っていたのだが、やっとわかった。『新・サンデートーク〜ごきげんよう草柳です』というテレビのCMで聞いたんだきっと。世の中には「時間をつくるひと」と「つくらない人」の2種類がある、と分類しているのが印象的だ。 2018/11/04
かおらべ
0
「時間をつくる人」と「つくらない人」の二種類がある という分類法に共感した。これから有限である人生の残りを生きるにあたり、時間をつくって生きていきたい。2025/01/14