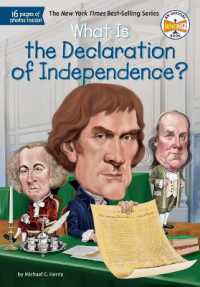- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
世界第2位のGDPを誇る経済大国、中国。だが実態はつかみづらい。その経済力が世界秩序を揺るがすと見る「脅威論」から、正反対の「崩壊論」まで、論者によって振れ幅が大きい。本書では、「中国の経済統計は信頼できるか」「不動産バブルを止められるか」「共産党体制の下で持続的な成長は可能か」など、中国経済が直面する根本的な課題について分析。表面的な変化の奥にある、中国経済の本質を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
109
西洋社会のような知的財産権保護の法律が徹底されていないゆえ、深圳では「パクリ」から「オープンソース」まで有象無象の電子機器産業が入り乱れてかえって活況を呈している。信用できる民間企業は経済音痴な政府とは無関係に「ミシュラン・ガイド」まで作っているので一見すると「中国すごい」と思う。ただ中央政府はその状態について法律を作って追認しているのではなく、あえて法律を作らず黙認しているだけ。体制にとって不都合が起きれば、いつでも「人治」に切り替えて締め付けをするので深く読むと「中国こわい」になる。2019/07/01
佐島楓
68
当たり前だが社会システムが大きく異なるため日本の常識が通用しない。トピックとしては経済問題がメインだが、格差の問題、特に農村と都市の戸籍の問題が興味深かった。それについても単なる居住地域による所得格差の問題ではないということは本書で初めて知った。2018/10/26
活字の旅遊人
37
最初のほうで統計の信頼云々という話題があったが、その後日本国の統計も知れたものであることが明るみに出ており、日本人読者としては恥ずかしい気持ちになってしまった。内容としてはしかし、さすが中公新書セレクト。決して古臭いとは思わせない。その中で最も印象深かったのは、第6章にあった「現代の中国政治経済体制は、権力が定めたルールの『裏をかく』ようにして生じる、民間経済のインフォーマル性を許容するだけでなく、それがもたらす『多様性』をむしろ体制維持に有用なものとして積極的に利用してきた」という指摘だった。2022/10/19
おさむ
34
共産党体制での成長は持続可能かに関する第6章が読み応えあり。MITのアセモグルらは中国は「収奪的な制度」で、長続きしないと断じているが、著者は中国は権威主義的な政府と非民主的な民間経済が一種の共犯関係にあると指摘する。意図せざる自生的秩序が国家による制度設計との緊張関係の中から生まれるのが特徴とする見方はなかなか腑に落ちる。多様性を体制維持に有用なものとして積極的に利用するしたたかさ。著者はますます西側のいうことを聞かなくなるのではないかと予想する。うーむ、やはり中国は一筋縄ではいかない国だと実感。2020/04/01
skunk_c
32
中国の大学での研究経験のある40代の研究者の手による、コンパクトな中国経済の現状についての概説書。これだけ変動の激しい中国について、具体的データをあげながら、また様々な分析手法を駆使(簡便な解説が嬉しい)し、あとがきにもあるように、感情論の対極を目指すような冷静で抑制の効いた筆致に好感が持てる。特に深圳のIT産業発展の分析は極めて面白かった。ハイエクの理論をこういう形で応用した書は初めてで目から鱗。文章もこなれていて読みやすく、扱われるテーマも広汎。中国の現状にについて考えるときの格好の参考書だと思う。2018/10/10