内容説明
現代社会は利己主義がはびこっているように見える。しかし人は、しばしば自分の身を危険にさらしても他人を助けようとし、困っている人を助けたいと願う。この利他的な感情はどこから生まれてきたのだろうか。ヒトを利他行動に駆り立てるものは、本能なのか学習なのか。共感、信頼、情愛はどうすれば育てられるのか――。脳科学、遺伝学、分子生物学の最新知見を交え、ヒトという生物、ヒト社会の本質に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
香菜子(かなこ・Kanako)
10
利他的な遺伝子 ヒトにモラルはあるか。柳澤喜一郎先生の著書。世の中の多くの問題はヒトが利己的で自分第一主義であることが原因。遺伝子で見るとヒトは利己的で自分第一主義であるのが定説だけれど、柳澤喜一郎先生のご主張によるとヒトには利他的な行動や感情を呼び起こす何かが潜んでいる。利己的ではなくて利他的なヒトが増えれば、人間同士の争いが減って、外交問題や紛争問題、地球環境問題も解決に向かうと思えました。2018/01/13
ステビア
8
利他性の話は最後にチョロっと出てくるだけ。進化や脳に関するエッセイって感じ。わかりやすいので目次を見て興味がわけばどうぞ。2014/04/20
とく だま
6
本能と言いながら、話しは倫理や道徳に及ぶ?利他心など遺伝子と環境による必然の出来事だと言いきって欲しい処 ^^;2022/05/12
村越操
4
人の心や行動の仕組みを解説した良書。人の知能は、年齢とともに環境の影響を受けにくくなり、代わって、生まれながらの遺伝的知能がより発現してくる。遺伝的に恵まれた能力があって、それを伸ばそうと努力するば、学習の効果を上げることができる。恵まれていなければ、成果は上がらない。記憶の容量に限界はない。冒険家や探検家は普通の人よりドーパミンが多く分泌されている、生まれつきのもの。人の態度や行動は、神経ネットワークの作られ方、そこで刺激の伝達に働いている神経伝達物質の変化によって変えられる・・・2012/05/30
小島輝彦
2
人には利他な面もあれば、利己的な面もある。どちらが良いとは一概に言えるものではないと思う。利己も利己で必要であるものであると考える。それでも、やはり利他の気持ちも必要で、両方があって成り立つ。その利他の気持ちの根幹にあるのが子供の頃の親、特に母親との関係であるとすれば、その関係を適切に育めるための社会の在り方も関わってくるのかもしれない。
-

- 電子書籍
- 【動画無し】漫画パチンカーMAX Vo…
-

- 電子書籍
- 魔王様にパフェを作ったら喜ばれました【…
-

- 電子書籍
- リビティウム皇国のブタクサ姫【分冊版】…
-
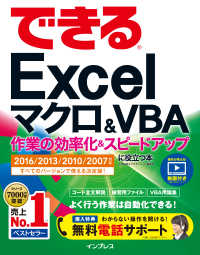
- 電子書籍
- できるExcel マクロ&VBA 作業…





