内容説明
ヨーロッパの国境は実に多彩で、陸上に国境をもたない日本から見ると、どれも自分の足で越えてみたくなるものばかりである。長い期間にわたってあり続けている国境もあれば、最近になって引かれた国境もある。現場で目にする景観は多岐にわたり、国境の歴史や人々の暮らしについての物語は果てしなく広がる地理学の眼をもって観察し、考えるヨーロッパの国境への旅、ゆっくりと楽しんでいただこう。
目次
1 ヨーロッパの国境の景観―地理学から見る国境の魅力
2 EUを象徴する国境を訪ねる(1)―ドイツ・フランス国境
3 EUを象徴する国境を訪ねる(2)―ドイツ・フランス国境
4 東西分断の国境を体験する―東西ドイツの国境跡
5 変わりゆく国境の姿を描く―ドイツ・チェコ国境
6 見えない境界を巡る―北イタリアの言語境界
7 国境に接する町を歩く―多文化都市ブラティスラヴァ
8 国境に消えた人々を追う―アウシュヴィッツ鉄道紀行
9 国境に紛争跡を探る―クロアチア国境
10 ヨーロッパを映し出す国境
著者等紹介
加賀美雅弘[カガミマサヒロ]
1957年大阪府に生まれる。1985年筑波大学大学院地球科学研究科博士課程単位取得退学。現在東京学芸大学人文社会科学系・特任教授。理学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
264
東西ドイツの統合、そしてEUの拡大とヨーロッパの国境の様子やあり方も甚だしく変容しつつある。私が旧東ドイツへの国境を越えたのはもう統合されてからであったし、列車であったので、いつの間に東ドイツ地域に入ったのかはわからなかった。ただ、車窓からの風景が単調になり殺風景になったといった変化は感じられた。他の国境越えもほとんどが列車だったが、最も劇的な変化を感じたのはシンプロン峠を越えてのイタリアからのスイス入りと、スロヴェニアからやはり峠越えでオーストリアに入った時である。今や国境といっても何があるわけでも⇒2024/09/16
パトラッシュ
111
欧州で国境を超える旅をするようになったのはシェンゲン協定以降なので、検問所で長く待たされたり綿密にパスポートを調べられた経験はない。それでも道路や橋を渡っただけで建築や言葉が変わり、いつの間にか空気まで変わっていると気付く。日本では味わえない感覚に浸りながら現地の大衆食堂で食事をとり、国境越えの気分を堪能するのが楽しくて毎年のように行っていた。コロナが終息して再び海外へ行ける日を願っていたが、ウクライナ戦争でロシア上空を飛べなくなった。平和ボケして今後も同じ日々が続くと思い込んでいたと痛感させられている。2022/08/28
鯖
24
「長い期間に渡って国境であり続けるものもあれば、最近ひかれた国境もある」前書きで既に考えさせられるのんきな島国の民である。アウシュビッツ鉄道紀行の章がやっぱり重かった。130万人以上のユダヤ人が国境を越えて貨物列車で運び込まれたのは鉄道網が発達したおかげってのがまた。ポイント通過するたびにあみだくじの曲がり角にのってるような気持ちになったという筆者。かなしい。2022/06/11
スプリント
21
島国に住む日本人にはピンとこない国境。 いまは友好国同士でも歴史を紐解けば領土の獲った獲られたで紛争とともに国境が定められたことがわかる。2022/08/09
つーちゃん
16
ヨーロッパの地理&歴史&文化の本をよく書く東京学芸大の特任教授による、ヨーロッパの国境の思い出アレコレ10選って感じの本。旅行行きたくなっちゃったと同時に世界史の近現代めっちゃ忘れてて焦った。ドイツ・フランスの間のアルザス人、イタリアとオーストリアの間のティロル人など、ハザマ系民族エピソードが面白かった!著者の指摘通り、国境付近の地域って、新型コロナとかの世界情勢の変化を最も受けやすいんだよね。戦争とかも。この先も国境を巡る物語は尽きない。2022/10/06
-
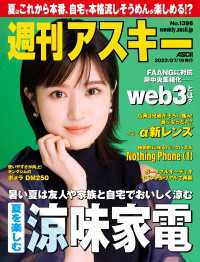
- 電子書籍
- 週刊アスキーNo.1396(2022年…







