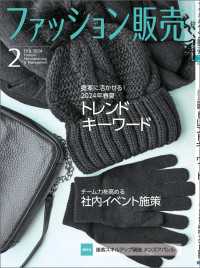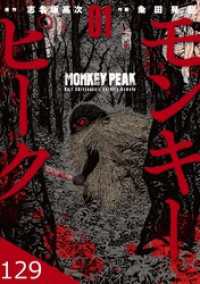- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「神は季節の変わり目に遠くから訪れ、村人の前に姿をあらわす」。師・折口信夫の「まれびと」論に目を開かされ、ハレとケのリズムとともに年を過ごす日本人の姿を追い続けた眼差しは、何を捉えてきたのか。正月や盆などの年中行事から、農村の田植えや漁村の海女、その他巫女や人形まわし――共同体の内に入って語り、距離を置いて眺めてこそ写し得た、日本古来の暮らしと生業。変貌し続ける伝承と習俗の真の姿がここにある。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
46
写真集。正月や盆といった年中行事、海女やイタコ、人形回しといった職業の数々、結婚式や葬儀といったハレの日、日々の営み。人生の様々な断面がここには収められていて、それらは一度も見たことがないのにどこか遠い日に見たような懐かしい場面ばかり。日本人の心の奥底に眠っているものが、ふと呼び覚まされるのかしら。撮られている写真はどれも五十から三十年くらい前のものだが、遥か昔にあった行事のように感じられる。地元の物もあるが見たこともなく、今現在これらがどのくらい残っているのだろうか。文庫版後書きに希望の光が見える。2014/12/07
ゆきこ
18
先に読んだ『祭りと芸能』と対になる一冊。昭和20年代から平成初め頃までの、日本各地の人々の生活が写真に納められています。どれも貴重な資料ですが、中でも興味をひいたのは、漁村の生活、海女、いたこです。もう少し詳しく知りたいと思いました。2024/04/01
広瀬研究会
8
前の巻でとりあげられた芸能や行事には素直に感動できたけど、今巻の職業や仕事についてはちょっと考えさせられました。生産性が伴わなければ変化するのもやむを得ないし、家業を継ぐのがいやで故郷を飛び出した若者もいただろうし、何だか寂しい気持ちになった。それでも丹精こめてまじめに働く姿はやっぱり貴くって、そういう記憶を残すことで、未来の誰かの温故知新につながって行くんだろうと思いたい。2018/04/23
荒川ながれ
7
2016/11/25 角川文庫 1,280円+税 ほんの少し前の、昭和30年を中心とした日本の姿が写真で見れる。日本古来の暮らしと生業が興味深い。昭和20,30年代は地域によってはまだ自然・神に近い暮らしがあった。今は情報テクノロジーも発展し、均一化された社会になり、分離されてしまっている。日本人の服装にしても、わたしの祖母は死ぬまで和装だった。最近は和装の老人は見ない。ユニクロっぽい服装になっている。宮本常一の本を読みたくなる。2023/08/22
うえ
7
千歯こきやもみすりなどの貴重な写真が並ぶ。後半の論考、悲しき南島の稲作も興味深い。「喜界、沖永良部、与論島は隆起珊瑚礁の石灰層で、水が溜まらない。その時限りの雨水による天水田なのである…きびしい風土の中での稲作の収穫量が、きわめて乏しい…奄美諸島の米は有史以来商品として流通機構に乗ったことは一回もない。自家消費にあてても主食を芋類でおぎなってきた…昭和三十一年…その年の経済安定本部は…「もはや戦後ではない」と、高度成長への繁栄の出発を宣言していた。南の離島にまでその言葉はとどいていなかった」2017/11/05