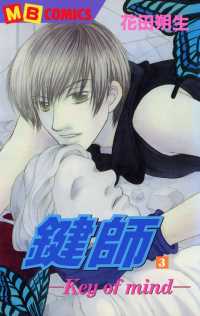内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
江戸時代の代表的な古地図である「大坂大絵図」を題材に、大阪の地誌や生活文化を探求する案内書。俯瞰図と部分拡大図の両方から謎解きを試みる「読み解きスタイル」という独自の趣向で、元禄時代の絵図をすみずみまで味わい尽くす。通常は手で触れることすらできない約300年前の貴重な古地図を、虫眼鏡で細部を鑑賞するかのような面白さで、大阪の歴史文化や地理地形もわかる本。俯瞰と部分拡大のカラー古地図を約150点収載。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マカロニ マカロン
16
個人の感想です:B+。『春琴抄』読書会参考本。読書会の時に大阪船場の道修町周辺の古地図を眺めていて、不思議だったことが本書で理解できた。江戸時代の町割りは通りの両側は同じ町名。次の通りは別の町名になり、1ブロックの真ん中で町名が分かれる。先月の『べらぼう』散歩の時の新吉原遊郭の地図も通りを挟んで同じ町名で、裏で分かれるのが不思議だったがQED。江戸時代の大阪(大坂)は人口40万人で武士は家族含め約8千人(江戸は約5割)で、町人の町だった。大坂は八百八橋と言われるが、実際には元禄4年に111橋だったという2025/06/05
ザッハトルテ
0
大坂の街の成り立ちが理解できてよかった。土佐堀、江戸堀などの堀川は、土地の嵩上げと水運のための水路作りの一石二鳥でできたものなのか。今はその一部が町名として残っているだけだが。2021/10/10
わ!
0
いつもながら、本渡さんの本は面白い。本当に大切に古地図を見ているという感じが伝わってくる内容だ。考えてみれば、江戸時代の人もこのように、地図を広げて、バーチャルな小旅行を楽しんだのかもしれない。だから古地図には、小さなお土産用のような古地図も存在するのだろう。つまり、人がより強い刺激を欲するようになっているだけで、やっていることは江戸時代も今もさほど変わらないことをやっているのかもしれないのだ。やはり人はいつの時代も人ですね~。2019/05/07
Tsuchi(TSUCHITANI.K)
0
歩いてみないと、わからないか2021/03/24