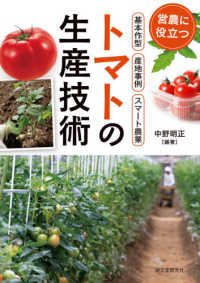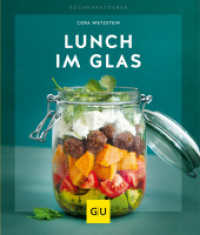内容説明
国民皆年金・皆保険と社会保険方式を特徴とする日本の社会保障。雇用の安定と人口増加のもと発展してきたが、1990年代以降の経済低迷により、家族と雇用のあり方は激変。社会的孤立などの問題が浮上した。加えて、人口減少が社会保障の土台を揺るがしている。「ミスター介護保険」と呼ばれ、地方創生総括官も務めた著者が現状の問題点を指摘し、孤立を防ぐ方法、高齢者偏重から全世代型への転換など新しい方策を示す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
26
個人的にこれからの社会保障は制度として維持できるのか、どう変わっていくのか気になっていることもあり、興味深く読むことができた。戦後設計された社会保障制度は、家族の構成の変化、雇用システムの変化、また、そこから派生してうまれた社会的孤立や格差など、当時は予期していなかった社会の変化に直面し、そしておそるべき人口減少時代の到来を目前にして、社会保障はどうあるべきか、なにができるのか、ということが丁寧に語られている。元々現場の行政に携わった官僚によって書かれた本であり、非常に実務的で読み応えのある一冊であった。2019/02/11
funuu
20
しばらく前に実家の古い箪笥を整理していたら昭和40年代の新聞に「日本はこのまま人口が増加すると食料不足になるから何とかしないといけない。」の主旨のコラムが掲載されていた。この危機感に基づいて官僚が人口抑制政策をとったようだ。中国の一人っ子政策と同じ。どうやら先の大本営と一緒で失敗した。「我が国の社会保障は、一つの企業に長い間、正規雇用として勤める場合には特段の支障はない。しかし、正規雇用とそれ以外の「二つの世界」を行ったり来たりするような人々にとっては、実に利用しづらい仕組みになっている。2018/02/03
おさむ
20
安倍首相はこの本を果たして読んだのだろうか。ミスター介護保険と言われた元厚労省官僚の著者が唱えるのは、全世代型の社会保障。この言葉の裏側には高齢者の給付カットという劇薬が含まれているのだが、選挙ではあまりふれられていない。著者は同時に地域連帯の必要性を説いています。人口減少と高齢化が同時進行する地方では、助け合いの共助がなければ成り立たないと言う危機感にも見えます。明後日は投票日。2017/10/16
ハイちん
14
少子高齢化が進み、ついに人口が減少する社会に突入した日本。ここで問題になるのが介護、育児などの社会保障における財源の確保と労働力の確保である。介護予防運動や定年の引き上げで生涯現役化を進めて社会保障を必要とする人をなるべく減らす。子育て支援を充実させて出生率を高める。金は使いやすい感じにまとめて柔軟に運用できるようにする。といった施策が書いてあった。今すぐ実行できれば社会は良くなるだろうが、人々の認識がそう簡単に変わるとは思えない。どうしても時間がかかるだろう。コロナも痛かった。2021/05/27
isao_key
13
「本書は日本の家族や雇用システムの変化、人口減少の到来という大きな社会変化が進行している状況を明らかにした上で、人口減少時代において、今後社会保障が目指すべき基本方向について考えるものである」と述べる。主要国の家族関係社会支出の対GDP比では、教育にかける割合同様、日本は1.26%と低く、イギリスの3.80%、スウェーデンの3.64%、フランスの2.91%に比べ半分にも満たない。フランス、スウェーデンの仕事と子育ての「両立支援施策」を見ると、手当額など水準の高さ、選別主義でない普遍的な支援展開をしている。2018/02/25
-
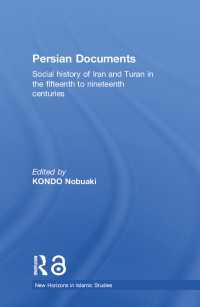
- 洋書電子書籍
- Persian Documents :…