- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
Amazonでも、googleでもない。
2020年、東京オリンピック後の日本社会を構想するヒント
阪急電車、宝塚歌劇団、東宝株式会社など、明治から昭和にかけて手がけた事業は数知れず。大衆の生活をなにより重んじ、日本に真の「近代的市民」を創出することに命を捧げた天才実業家の偉大なる事業と戦略とは?
【小林一三(こばやしいちぞう)の手がけた事業】
阪急、宝塚、東宝、阪急百貨店、第一ホテル(後の第一ホテル東京)、阪急ブレーブス(後のオリックス・バファローズ)、昭和肥料(後の昭和電工)、日本軽金属、東京楽天地など。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
23
著者が強調する小林一三の特質は2点。住環境と人口統計学の観点から戦略を立てる経営者であったこと、庶民の文化成熟度を重視する民主的文化主義者であったこと。人間を「数」と同時に「人」として見るバランスにおいて、参照すべき人物といえるのだろう。阪急百貨店や宝塚、東宝の経営に関しても、洗練された商品を多く販売することで安価を実現し、庶民の生活向上につなげるという思考を貫徹させる。面白いのは、宝塚が生んだ女性言語が谷崎を魅了し、その言語文化が神戸出身の村上春樹まで反映しているという論。こうした「余談」が魅力的。2022/02/07
yyrn
22
東京での銀行勤めを34歳で辞め、大阪で電車事業に関わったことを契機に沿線の開発、劇団、デパート、映画、野球団、電力など、次々と新たな事業を手掛けた小林一三(1873~1957)。その経営手腕を学びたくて手に取ったが、どちらかというと日本近代史を踏まえた経営者マインドを教えられた本だった。「清く・正しく・美しく」をモットーとする「宝塚&阪急文化」や、戦時下においても自由経済主義を信奉し、大戦直前に就任した商工大臣として統制経済を強める官吏や軍人たちと激しくやりあったことなどが綴られている。勉強になった。2019/07/23
すしな
19
143−21.海外から来た人たちがコンビニの食べ物を食べて驚くくらい日本は庶民が手頃な価格でクオリティの高いサービスを得られるますし、倫理観も高いとも言われますが、元々の素質だけでなくやはりこういう人の仕掛けがあって培われたものもたぶんにあるのでしょうね。もし阪急や宝塚がなかったりしたら、今はもっと都心と郊外の格差が広がっていたでしょうし、清く正しく美しく生きようと思う人も少なかったように思いました。2021/12/19
りんだりん
16
研修の課題書籍。阪急電車、宝塚歌劇団などを創設した経営者小林一三の物語。人口学に基づき、市民の願望に目を向けて数々の事業を成功させてきた著者の考え方やビジネスの進め方は、当時の人口が爆発的に増えている時代に適したものだった。現在はそれとは逆に人口減少時代。小林一三がとった人口増加時代のやり方から対偶的に学ぶべきものがある。★22021/09/26
templecity
15
三井銀行時代は余り出世にも恵まれなかった小林だが、見合いで結婚したが愛人を捨てきれず二度結婚しているが、結果的に良い家庭を築けている。鉄道発展の考えは都市部における人口増の傾向を読み取り、郊外の環境の良いところに住宅地を設ければ、不動産と鉄道運賃収入の両方を見込めるとの先遣の銘であった。宝塚歌劇団を作ったのは有名な話。百貨店を作ったが東京の三越などが高い値段で送迎をつけて客を呼び込んだが、ターミナル駅に作ったので多売薄利の考え方とした。(続きあり)2019/09/04
-

- 電子書籍
- 天才少女は重力場で踊る(新潮文庫nex…
-

- 電子書籍
- いきなり大魔導!1 アース・スターノベル
-
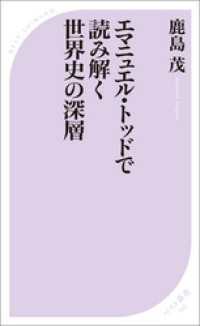
- 電子書籍
- エマニュエル・トッドで読み解く世界史の…
-
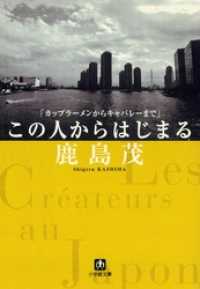
- 電子書籍
- カップラーメンからキャバレーまで この…
-
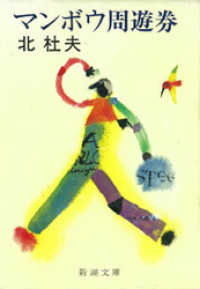
- 電子書籍
- マンボウ周遊券




