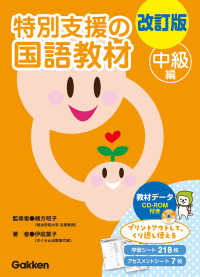内容説明
自然界には脳がなくても賢くふるまう生き物がたくさんいる。著者は専門である制御工学の研究を通じ、「知能の源は、環境との相互作用にあるのでは?」という仮説に至った。そして、「現象学」という哲学思想を取り入れて論拠を固め、さらに、生き物っぽく動く「ムカデロボット」を作り、その実証を試みる。人工知能、知能、制御に関心のある読者はもちろん、現象学に関心のある読者にも、お勧めの1冊である。
目次
第1章 旅の始まり 第2章 知能はどこにあるのか 第3章 制御の「メガネ」で知能を見る 第4章 制御の「技」を身につける 第5章 奥義「陰陽制御」を会得する 第6章 i-CentiPotで知能の謎を解く 第7章 旅の終わりと新たな始まり
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
PenguinTrainer
9
知能を持っているかのような振る舞いをする単純な制御則で動くロボットの話。 多足のロボットの場合、一つ一つの足を制御するのは複雑過ぎるが、柔らかい足を規則的に動かすだけで知能を感じることを一部現象学的にとらえた本。2021/12/17
Танечка (たーにゃ)
4
障害物があれば避け、その後元の進行方向に戻る、知能があるようにふるまうムカデロボット「i-Centipot」開発の裏話。普通、知的ロボットを作る課題を与えられたら、「センサーを積んで」とか「機械学習」とか考えてしまいそうだが、最終的に使われたソリューションはとてもシンプル!シンプルすぎて、逆に、「我々が知能を見出している対象とはいったい…?」という哲学的な謎に挑むことに。著者の専門である制御学の説明は難しかったが、目標に向かってトライ&エラーを繰り返していることがわかるエピソードは門外漢でも楽しめる。2019/03/22
issy
2
環境を外乱と見て制御則により解消しようとする従来の制御(陽的制御)の考え方から、制御対象と環境の間にある相互作用により望ましい結果が得られると考え、その相互作用を陰的制御とする考え方への転換のプロセスを著者の研究履歴を振り返りながら追体験していくような構成。陰的制御は環境との相互作用に起因するがゆえに、定式化はできるが(事前には)計算できない。何かに「知能」の存在を感じる時、そこに存在する制御則として、陽的制御と陰的制御が組み合わさっている、という視座の提起。2022/10/31
gachin
2
知能を現象学的に理解するのは妥当だと思うけど、一度ここまで到達すればあとは「自分が何故そう思うのか」という自分語りで不可避的に独り善がりになりがちな印象。と思われそうな文体なのが勿体ない。ヒトがついつい見出してしまいがちな制御則に「陰的制御」と命名し、”只の観察者の幻想”と切り捨ててしまわないのは面白かった。肝は「定式化できる・アテにはできるが、計算はできない/しない」とし無限定環境に対応する点。理学は順制御則(制御則を陽に作る)よりも逆制御則(観察から制御則を推測する)と相性が良いので、大事な視点だ。2021/03/23
こん
0
ユクスキュルの環世界説とかも思い出しながら前半を読んでいたけど、後半はちょっと難しかった。2024/04/23
-
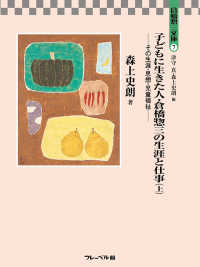
- 電子書籍
- 子どもに生きた人・倉橋惣三の生涯と仕事…