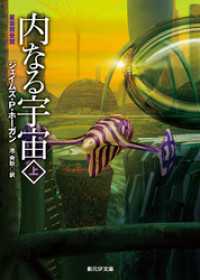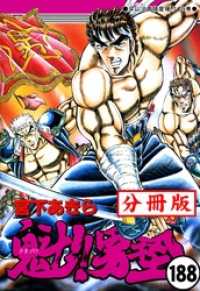内容説明
仏像鑑賞が始まったのは、実は近代以降である。明治初期に吹き荒れた廃仏毀釈の嵐、すべてに軍が優先された戦時下、レジャーに沸く高度経済成長期から、“仏像ブーム”の現代まで、人々はさまざまな思いで仏像と向き合ってきた。本書では、岡倉天心、和辻哲郎、土門拳、白洲正子、みうらじゅんなど各時代の、“知識人”を通して、日本人の感性の変化をたどる。劇的に変わった日本の宗教と美のあり方が明らかに。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
27
仏像ブームの昨今、仏像を巡る日本における宗教と美術の関係を、江戸時代の御開帳からいとせいこう・みうらじゅん両氏「見仏記」までの流れに沿って論述した労作。ありそうでなかったテーマで非常に面白かった。和辻哲郎(古寺巡礼)は、仏像は美術品だと考えた。亀井勝一郎(大和古寺風物誌)は、仏像は美術品ではなく信仰に対象だと信じた。白洲正子(十一面観音巡礼)は、仏像は美術品として美しいからこそ、美か宗教ではなく、美ゆえに宗教なのである、と鮮やかに切り分ける。土門挙と入江泰吉の仏像写真に対するスタンスの違いも興味深い。2018/08/28
trazom
24
仏像は美術品として鑑賞の対象だと考える和辻哲郎(「古寺巡礼」)、美術品ではなく信仰の対象だと主張した亀井勝一郎(「大和古寺風物誌」)の対立を経て、白洲正子さんが「仏像は美術品として美しいからこそ、俗世を超えた感動を与えてくれる。美か宗教かではなく、美ゆえに宗教だ」と言っているのは極めて説得力がある。ただ、昨今の安易な観光ブームを憂える一人として、梅棹忠夫先生の「観光は、人間を傲慢にする」という警鐘や、高村光太郎の「夢殿の救世観音は、秘仏として秘封し奉る方がいい」という畏怖の感性に、共感を覚える。2018/11/09
yutaro13
18
「信仰」の対象から「鑑賞」の対象へ。本書は明治以降の日本人と仏像との向き合い方を鮮やかに浮かび上がらせる。大正期に美術・教養としての仏像鑑賞を打ち出した和辻哲郎『古寺巡礼』と、戦時期に「鑑賞」から「信仰」への転向を示した亀井勝一郎『大和古寺風物誌』の対比は興味深い。戦後には仏像を鑑賞することで得られる感動を仏への信仰と同じものだと信ずる白洲正子が登場するが、仏像鑑賞が著しく大衆化された現代において、私自身の仏像との向き合い方はどうだろうか。本書を読んだ京都・奈良に向かう新幹線の中で、改めて考えさせられた。2019/03/03
りらこ
13
博物館に展示されている仏像をきちんと初めて見たのは確か中学生の時。え?お寺にあるものなのに良いの?と思ったのを鮮明に覚えている。おそらく自分のなかに宗教としての仏像はあっても、美を感じる対象としたものではなかった。あの時感じた原始的な感情もまたこの本は解き明かしてくれている。江戸期の御開帳から始まり、廃仏毀釈、フェノロサ、和辻哲郎、戦時中の仏像写真への救済を求める心、土門拳と入江泰吉が撮る仏像、そして白洲正子、みうらじゅんといとうせいこうの見仏記に至る流れがよくわかり、その見方に納得したり疑問を持ったり。2018/08/30
ムカルナス
11
明治維新により信仰の対象から美術鑑賞の対象となった仏像と日本人がどう向き合ってきたのかを時代ごとに分析。信仰心を持たない仏像めぐりは邪道だという人がいる一方、信仰心はないが仏像に惹かれる人々は仏像への愛がやがて信仰心にも似た気持ちへと変わっていくのを発見する。寺社探訪が好きな私にとっての鑑賞の対象は建物、お庭、日本画であり仏像ではない。しかし信仰の対象である仏像をスルーするのは(形式的に拝んだとしても)どこか後ろめたさがつきまとう。その後ろめたさは現代の寺院にとっては信仰か観光かの問題に繋がるのだと思う。2019/06/19