内容説明
興福寺中金堂再建までの25年の歩み。幼い頃、荒れ果ててしまった興福寺を見て哀しかったと語る著者・多川俊映(現 興福寺貫首)は、「自分の代で天平の頃の美しい伽藍を復元する!」と心に誓い、境内の整備に邁進してきた。四半世紀の時を経て、2018年10月についに落慶となった中金堂の再建は、その中核をなす大事業。本書は、その再建に費やした25年間を丁寧に追った一冊。まずとりかかったのは柱にする良質な太い木材を探すこと。現代の日本ではもはや見つけることができず、なんと! アフリカはカメルーンから輸入することを決断する。その壮大な発想力と実行力からは、この大事業にかける貫首の情熱と執念が伝わってくる。
目次
はじめに
第一章 境内整備と中金堂再建を志すまで
コラム(1)興福寺を去った仏像・残った仏像
第二章 ついに動き出した「天平の文化空間の再構成」
コラム(2)薪御能と塔影能
第三章 発掘調査と中金堂再建のプロセス
写真で見る中金堂再建のプロセス
第四章 新たなる礼拝対象「平成の法相柱」再興
コラム(3)法相唯識の「阿頼邪識」
第五章 木材と瓦、職人たちの力を結集
その一 柱になる木材を調達する
その二 目指すは一〇〇〇年もつ瓦
興福寺の至宝 仏像との新たな出会いのために
興福寺略年表
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
24
百万遍の有難い言葉や文書よりも、実物を見て感じた方がその後に残る印象は間違いなく大きい。だからどんな民族でもせっせと有難いモノを創るし、失ったら復元しようと頑張ってしまうのは人類のDNAに埋め込まれた性のようなモノなのだろう。奈良や京都の寺院を散策していると落ち着くし、日本人に生まれてきて良かったなと思うので、この本で詳しく紹介されている興福寺中金堂再建のための60億円は納得だが、ただ日本国内では直径1mを超える木材はもはや入手困難だからアフリカまで探しに行かなければならなかったとは誠に残念。林業ガンバ!2020/09/22
Kikuyo
13
710年創建された奈良の興福寺中金堂の再建の歩みについて。年輪幅の均等な強度あるヒノキを海外から調達、「平成の法相柱」再建など興味深かった。コラム①「興福寺を去った仏像は」時代の流れの中、損傷を受けながらも奇跡的に残った仏像たちがたびたびの災禍をくぐりぬけてきたことを考えると文化財を守り伝えることの重みを感じさせられる。2020/12/28
ルアット
3
澤田瞳子さんの「龍華記」を読み終わったときに、たまたま図書館で見つけて目に止まった。何年か前に、興福寺から平城宮跡、唐招提寺と歩いた時の記憶が蘇ってきて、懐かしい思いがした。今思うと、よく歩いたなと思う。2019/01/01
まさちゃん
0
ちょうど興福寺の中金堂を見てきたばかり、よくわかりました。今のお堂はハイテクであり天平であり、そこにかかわっている人たちの思いが伝わってきます。2018/12/05
-

- 電子書籍
- パチンコ必勝ガイドMAX 2025年0…
-

- 電子書籍
- ワケあり婚41 NETCOMICS
-
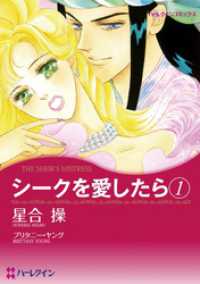
- 電子書籍
- シークを愛したら 1【分冊】 11巻 …
-

- 電子書籍
- Love Jossie 先輩、おジャマ…
-
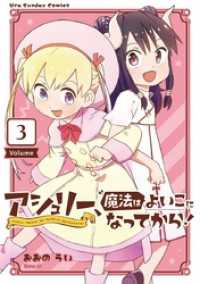
- 電子書籍
- アシュリー、魔法はよいこになってから!…




