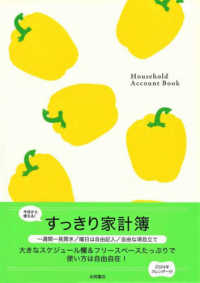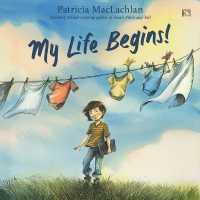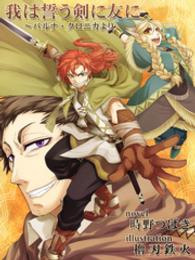- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
非正規労働者のうち、パート主婦、専門・管理職以外の人々は、日本には約930万人いる。その平均年収はわずか186万円で、その貧困率は高く、女性ではそれが5割に達している。いじめや不登校といった暗い子ども時代を送った人が多く、健康状態がよくないと自覚する人は四人に一人の割合である。これら「アンダークラス」に属する人びとを、若者・中年、女性、高齢者と、それぞれのケースにわけ、調査データをもとにその実態を明らかにする。今後の日本を見据えるうえで、避けては通れない現実がそこにある。
目次
序章 アンダークラスの登場/第一章 新しい階級社会の誕生/第二章 アンダークラスとは何か/第三章 現代日本のアンダークラス/第四章 絶望の国の絶望する若者たち──若年・中年アンダークラス男性の現実/第五章 アンダークラスの女たち──その軌跡と現実/第六章 「下流老人」が増えていく/第七章 「失業者・無業者」という隣人たち/第八章 アンダークラスと日本の未来/終章 「下」から日本が崩れていく/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
351
著者の橋本健二氏は社会学者。手法は統計を駆使して、そこから現代社会を考察するといったもの。本書では、アンダークラスの実像に迫る。著者によれば、現代の階級は「資本家階級」、「新中間階級」、「労働者階級」、「アンダークラス」+従来の「旧中間階級」ということになる。アンダークラスは、本来は労働者階級に属するのだが、主に正規雇用/非正規雇用によって階級が分断されたとする。男性と女性とでは様相を異にするのだが、とりわけ男性において負の連鎖から逃れられないようだ。唯一の希望はアンダークラスの男性は「日本の現状を⇒2023/06/01
夜間飛行
125
この用語を使うこと自体ためらわれる。自分がどちら側にいるかは才能や努力より運なのだ。データを見ると親の収入、教育環境、いじめが関わっている。女性の場合は親の収入や家庭環境よりいじめ・不登校・離死別の影響が大きい。アンダークラスに対する差別的なレッテル貼りは最悪だ。読んでいてとりわけ辛く感じたのは、嫌な仕事に回りたくない正規労働者が、昔なら同じプロレタリア階級とされたアンダークラスに対して冷淡だという指摘である。自分もその一人だから偉そうなことはいえないが、彼らの政治的自立なしに民主主義はあり得ないと思う。2019/08/01
こばまり
58
畳み掛けるデータ分析により実像を明らかにされ、すっかり説得されてしまったがさてどうしよう。焦燥感に包まれる。加齢に伴う疾病や期待外れの年金支給額等々、一握りの特権階級を除き、アンダークラス化はもはや遅かれ早かれの問題だ。2018/12/26
rico
49
年収186万。非正規雇用労働者を中心とした「アンダークラス」の実態を様々な調査結果に基づいて明らかにする。そこに至る主なきっかけは、男性は新卒時に安定した職に就けなかったこと、女性は離・死別でシングルになったこと。日本の福祉が企業等の勤務先に依存し、公的セーフティネットが貧弱であること裏付ける。人口動態、産業構造の変化、増える外国人労働者。状況はますます厳しくなるのに、本気で向い合う動きはほとんど見えない。「一歩間違えば誰でも」という暗黙の危機感が自己責任論と結び付き問題を覆い隠す。まず可視化が重要か。2019/01/16
おかむら
46
下層階級なんて自分には関係ないと思ってはいられない怖い本。運が悪ければいつでも転がり落ちる可能性が…。バイト学生やパート主婦など家計の足し的非正規雇用を除いた、主たる家計が非正規の収入のみの人々の実態。ただ統計データって最近信用できないような気も。統計から漏れたところに真実がありそうだよ。それと日本のアンダークラスは当人たちも「自己責任」って考え方がまだ主流だけど、海外のようにその不満が政治に向かうようになるのか? 排外主義との親和性も気になるところ。2019/02/06