内容説明
「知者は“心のある道”を選ぶ。どんな道にせよ、知者は心のある道を旅する。」アメリカ原住民と諸大陸の民衆たちの、呼応する知の明晰と感性の豊饒と出会うことを通して、「近代」のあとの世界と生き方を構想する翼としての、“比較社会学”のモチーフとコンセプトとを確立する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
59
人間(ヒト)とは、一体、何なのか・・という根源的な問いかけをされた気分。ヤキ族の対話を入口として、自分自身の奥深くに分け入るような感覚を持ちながら、読み進めた。眼に見えるもの、頭で考えることを是として、そこに留まっていることを再考する。それは、ある意味、囚われていることでもある。言い古された言い方になるが、五感で感じ取ること、さらに、今を是としないこと。あるがままの状況を、まずは受入、そこから派生することへ、心を向けること。人と言う字の成り立ちを考える。2022/11/11
うえぽん
49
社会学者が、比較社会学研究を進める前のモチーフ作りとして、旅の終わりに、人類学者とメキシコ・インディオとの出会いの分析を通じて、近代を相対化し、自我の深部の異世界を解き放つべく書かれた本。インディオの生き方は、近代世界の自己完結的な世界からの超越と、無数の世界を含んだ「世界」への再内在化を促すと言う。彼らの理想の知者となる途上には、恐怖、明晰、力、老いという敵があるとする。意思は耽溺の反対語で反惰性化する力で、明晰は盲信だとする。独特の筆致と象限に分けた分析から自らの固定観念も掘り崩す力を感じる。2025/01/22
サゴウ
48
とにかくすごかった。真木悠介(見田宗介)の代表作とされるが、既存の世界の枠組みを溶かしてくれるような素敵な概念がたくさん詰まっている。ドン・ヘナロの老練な思想が美しい。「トナールとナワール」、「世界を止める」の2概念が特に良かった。現代人の多くに読んでもらいたい本。2023/09/10
特盛
38
評価5/5。別途読んだ「自我の起源」に続き、著者は天才だと改めて敬服する。70年代に書かれたコミューン論、しかも人類学を下敷きにというと古臭さとうさん臭さしか予感しなかった(実際、序盤は半信半疑だった)が見事に裏切られた。共同体だけでなく個としての「生き方の問題」に非常に知的に洗練されたフレームワークを提示され刺激になった。明晰の罠からの解放、制御された愚かさ、意味の疎外からの解放の為の心のある道。本書で描かれるこれらのヒントには、ニヒリズムの虚無を含め、生き方に迷う人にとってなんらか光を照らすに違いない2025/05/01
逆丸カツハ
32
なかなかどうして面白かった。具体的に書きはしないが 、本と本が結びつく時、知識と知識が結びつく瞬間ほど面白いものはない。2025/05/18
-

- 電子書籍
- MONOQLO 2025年1月号【電子…
-

- 電子書籍
- ジャイアンツ愛 原辰徳の光と闇
-
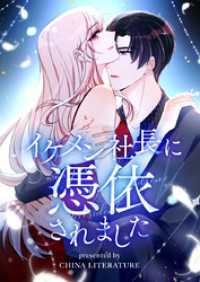
- 電子書籍
- イケメン社長に憑依されました【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 美女と賢者と魔人の剣(3) ぽにきゃん…
-
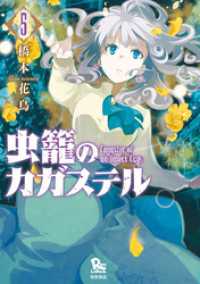
- 電子書籍
- 虫籠のカガステル(5)【特典ペーパー付…




