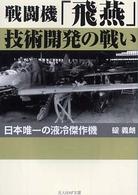- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
知ってるつもりだった会社の意外な仕組みや歴史が、面白いように分かってきます。次々に謎が解けていく様は、まるで推理小説のよう! 読後にはジワリと希望がわいてきます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kawai Hideki
98
企業、会社、法人、株式、といった経済活動の基礎的な要素について、その根本定義に立ち返って歴史的変遷を説明し、さらに、21世紀の会社の姿がどのようになるかを予測する本。非常に分かりやすかった。特に株式会社にはヒトとモノの二つの側面があり、株式会社を完全にモノ化する方法と完全にヒト化する方法があること、は勉強になった。また、「脱工業化社会」や「知識社会化」や「第三の波」といった、トフラーやドラッカーが唱えていることが、資本主義の枠組みがもたらす必然の結果として、一つの理論ですっきりと説明できており、感動した。2015/01/04
かなすぎ@ベンチャー企業取締役CTO
17
「会社はこれからどうなるのか?」というより、「会社とはなにか?」「法人とは何か?なぜ法人という概念が生まれたのか?」「資本主義とは何か?」という問いに答えてる。めちゃくちゃおもしろい本。会社で働く人は、みんな読んだ方がいい。もちろん、経営者や起業家の人は言わずもがな。まだ考えは完全にまとまりきれていないが、会社での不祥事や、パワハラでの自殺などは、すべて「法人」が「法人」であるがゆえに起きてるのかもしれない。「ヒトであって、モノである」という矛盾が生み出したバグの結果なのかなとか考えるきっかけになった。2022/02/26
ほし
16
とても分かりやすく、勉強になりました。法人には大きく分けて、株主の権限が強い法人名目説的なあり方と、権限が弱い法人実在説的なあり方が考えられ、日本における会社の多くは後者の実在説がとられてきたということ。それは、結果として社員が同じ会社に長く勤めることを可能にし、終身雇用制度も相まって、社員が組織特殊的なスキルを身に付ける動機となったこと。80年代頃まではそあり方が産業資本主義に非常にマッチし、大きな利潤に繋がったのですが、ポスト産業資本主義の現代には対応できていないという問題があることが語られています。2019/07/16
中年サラリーマン
15
良書。「会社というもの」の将来をネタに議論は進んでいく。まず日本型とアメリカ型会社の違いを述べ、それらは同じ概念が違った現れ方をしたものだという議論。そこでなぜ日本は日本型会社になったのかを述べるとともに昨今の不況に対する日本型会社の立ち直りの遅さを分析する。さらにポスト産業社会に対する言及も。一気に読んでしまった。2013/09/01
Mc6ρ助
14
『いくら工場システムによって労働者の生産性が上がったところで、それに応じて労働者の実質賃金が高くなってしまえば、利潤は生み出せません。生産活動から利潤が生み出されるためには、販売収入が生産費用を上回っていなければなりませんが、・・・労働生産性と実質賃金率とのあいだの差異性こそ、産業資本主義の利潤の源泉なのです。(p235)』ポスト産業資本主義時代のはずの令和の日本、実質賃金率を抑えてきて、今がある。閑話休題、2003年の名著今でも色あせず日本の会社が何ものかを解き明かしてくれる。2021/04/06