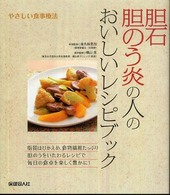内容説明
2011年3月11日に東日本を襲った大地震と大津波、それにともなう福島の原発事故は、実際上の問題だけでなく、公共哲学という“善き公正な社会を追求し、現下の公共的問題を考える”学問にも様々な問いを投げかけることとなった。それらに今どのように応えるのがふさわしいのか。日本における第一人者が、議論の手がかりとなる有力な学説を紹介しながら、3・11以降の社会を考えるための羅針盤を提示する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sk
4
3.11に対して公共哲学の立場からの応答を試みたもの。様々な哲学者の立場を著者なりにアレンジして工夫を試みているが、今一つ踏み込みが足りないかもしれない。2018/10/08
Bevel
1
「(...)公共哲学は、諸学問を横断・媒介し、それぞれの学問がどのような公共的問題と絡むかを伝えるようなトランスディシプリンとして理解されるべきでしょう」(129)とか「他者と分かち合えるイメージの喚起力」としての「公共的想像力」が重要だというのはよいけど、結局具体的な問題に対応した経歴もないし、別の学問側の視点に立った記述もゼロだから、説得力がないんだよなあ。ポパーの「漸次的工学」、「べき」論が「できる」論を含まないといけないという『歴史主義の貧困』の話が面白かった。 2021/07/30
むとうさん
1
実は以前この人の講義を受けたことがあるのだが、表面的にはなぞれても結局何が生まれるのかさっぱりだった。4年ほど経って同著者の本を読み直してみたが、やっぱりわからない。ただわからない理由はなんとなくわかって、多分「公共」というものが何なのかハッキリしないのだ。加えて結局今どうしてこのような問題がおきているのかというのにはノータッチ。それでこの理想は実現できるんですか。現状って支持する人がいるから起きているんだけれど、彼らをどう説得するんですか、あるいは無理矢理変えるんですか、それは公共的なんですか…等等。2012/09/22
AR読書記録
1
まずは「公共哲学」というものを知らなかったので,目からうろこがぼろぼろ.このなかで括弧付きであげられる沢山の言葉がどれもこれもとても重要な言葉なり概念だと思う.全部把握できるまで,何度でも読みたい.それにしても「公共」.たとえ望まないとしても社会で生きる人間,他人との関わりは持たざるをえません(直接的なものでないとしても,視野に入るというだけの意味でも).その点だけでも他者への意識(配慮)は必須なはず.「個人」を大事にする意識がすごい勢いで(過剰なまでに)浸透したことを思えば,これからは是非逆方面を.2012/04/26
たかし
0
「活私開公」の価値感。国≠公。 ①義務、②徳、③公共善・公共悪の3つの倫理からなり、①・②は人間の行為、③は社会制度。①義務倫理は「活私開公」と「滅私開公」の連携のための基礎であり、A.道徳義務(尊敬に基づいた行為の必然性)とB.法義務(外的な強制力)がある。②徳の倫理は、「活私開公」を支えるための基礎であり、アリストテレスの賢慮、東洋の仁義礼智、A・スミスの勤勉・節約など。③は公共善と公共悪は社会制度と政策の基礎であり、ローマ共和制、トマス・アクイナスの共通善、現代では医療・年金・教育・金融などの諸制度2011/12/25
-

- 電子書籍
- おとなの恋は、やぶさかにつき。 31 …
-
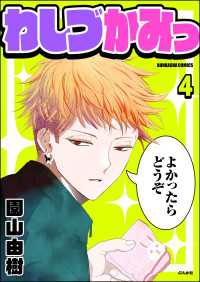
- 電子書籍
- わしづかみっ(分冊版) 【第4話】 主…
-

- 電子書籍
- BNPL 後払い決済の最前線 急成長す…
-
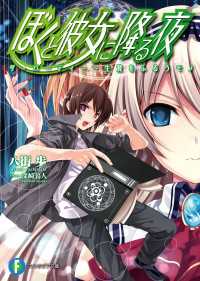
- 電子書籍
- ぼくと彼女に降る夜4 ザ・パーティー~…