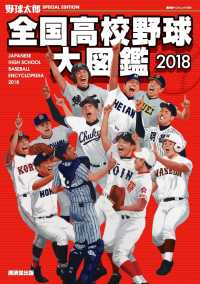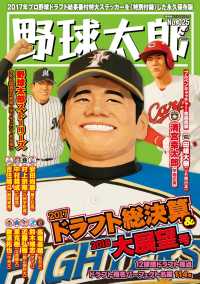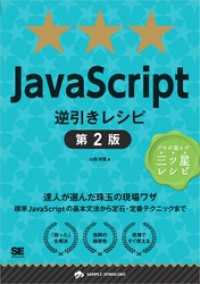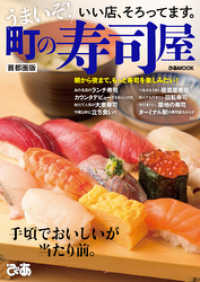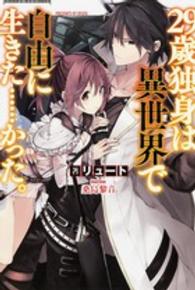内容説明
清水幾太郎、林健太郎、丸山眞男、福田恆存……。彼らが活躍した論壇誌はいかなる問題を、どのように論じてきたか。論壇が存在感を持っていた時代を鮮やかに描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
12
現在では存在感が小さくなった「論壇」の歴史について、1945〜70年まで、岩波書店の『世界』を中心に概説している。丸山眞男を始めとした、様々な知識人の思想への理解が深まった。学生たちが総合雑誌を読み、政治や文芸について議論していた時代は遠い昔なのだなと感じるとともに、ネットはテレビに比べれば文字文化ではあるが、誰でも簡単に参加できてしまう点から、論壇の形成は難しいのだろうなと思った。2019/06/02
うえ
3
「スターリン批判やハンガリー事件によって社会主義の威信が揺らぐ一方、日本社会では高度経済成長による大きな構造変動が始まりつつあった…福田恆存が「平和論の進め方についての疑問」を書き、1954年という早い段階で、『世界』に集う知識人の平和論に一石を投じたのも『中央公論』が舞台だった。中間文化という概念で時代の構造変動に切り込んだ加藤秀俊「中間文化論」も、中央公論57年3月号に載った…加藤は…日本文化を、高級文化中心・大衆文化中心・中間文化中心という三段階に分け、すでに現在は中間文化の時代に入っていると指摘」2024/07/01
バルジ
2
戦後隆盛を極めた『世界』をはじめとする論壇を概観する。竹内洋の『革新幻想の戦後史』や『丸山真男の時代』等と合わせて読むとより楽しめる内容。本書内で語られる「論壇」は主に『世界』であり、その点『世界』の戦後史と言ってもよい。今や死語に近い「論壇」なる言葉も、戦後間もない時期から一時世論形成に絶大な影響力を有していたことが本書から窺える。しかし「国家像」という大きな物語を語れなくなった60年安保以降の状態は、論壇の隆盛があくまでも「戦後」という特別な時間での一過性の現象に過ぎなかった事を教えてくれる。2019/11/23
tkm66
0
ちゃんと抑制が効いている。多少「えーっ!?」って箇所はあるが。2018/11/22