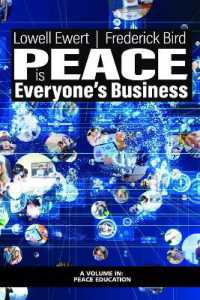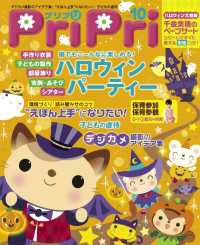内容説明
数学はもっと人間のためにあることはできないのか。最先端の数学に、身体の、心の居場所はあるのか――。身体能力を拡張するものとして出発し、記号と計算の発達とともに抽象化の極北へ向かってきたその歴史を清新な目で見直す著者は、アラン・チューリングと岡潔という二人の巨人へと辿り着く。数学の営みの新たな風景を切りひらく俊英、その煌めくような思考の軌跡。小林秀雄賞受賞作。(解説・鈴木健)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
367
最初は数学史を踏まえながら、読者を徐々に「数」の世界に導いてゆく。知らなかったのだが、16世紀頃までは「=」の記号もなかったそうなのである。記号化をさらに徹底させて、「一般式」の研究にまで洗練させたのはヴィエト(16世紀後半)が最初であったらしい。ax(2乗)+bx+c=0のような一般式は彼を待って初めて生まれたのだそうだ。あまりにも当たり前のように思っていたが、数学史も奥が深いとの思いを新たにする。これに続いて登場したのがデカルトであり、ニュートン、ライプニッツ、オイラーと脈々と受け継がれていった。⇒ 2024/12/19
南北
93
読友さん本。知的好奇心を刺激してくれる好著。前半は数学史を外観したもので、負の数や虚数が当時の人々に理解できなかったのは、幾何学を起点としていたため、物理的にあり得ないものは認められなかったというのは腑に落ちた。後半は「数学は情緒である」で有名な岡潔の話が中心となる。天才が語る尖った言説のように感じていたので、積読本のままにしていたが、また読んでみようと思うようになった。「人間の認知は、身体と環境の間を行き交うプロセスである」という著者の言説が印象に残った。2021/02/16
夜長月🌙
81
数学にまつわる新奇な概念を伝える書。数学史、数学が生成する建築(例えば三鷹生命反転住宅)、数学→コンピューター→AI、数学的情緒。コンピューターを生み出した数学者チューリングの言葉。「学生が働き出すまでに20年かかるなら、思考するコンピューターにも20年いろいろな体験(登山、旅行、料理・・・)を積ませないとならない」。コンピューターが生まれるまでにすでにAI的な思考があったことを示します。2020/07/19
クプクプ
79
著者はレイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』の新訳をした森田真生さん。私は、新訳の『センス・オブ・ワンダー』を読んで、森田真生さんの専門は生物ではなく、数学の方なのかと仮定を立てて、『数学する身体』を読んでみました。私の狙いは的中し、『数学する身体』は面白く、そして懐かしさを感じました。懐かしさの正体は10年以上前に出版された、福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』の読後感に似ているところから来ていました。『数学する身体』は著者が数学者の岡潔の本に出会い共鳴し、完成したエッセイで読み応え十分でした。2024/12/27
コットン
77
若くて目覚ましい成果を上げた研究者である『独立研究者』という独特な立ち位置の著者による数学的歴史を追いながら身体能力と数学の関係性について論じている。数学者アラン・チューリングと岡潔についてスポットが当たっている。 余談としては自分の知識不足だが、近代哲学の父デカルトは記号代数の表記(未知数がx,y,zで既知数がa,b,c)を現代的な形に定着させた人だったとは知らなかった。2024/01/21