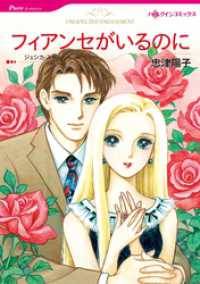内容説明
いまから140年前、ひとりのアメリカ人宣教師が海を渡って日本にやってきた。
トーマス・セロン・アレクサンダー、27歳。通称トム。
西南戦争が終わった年の秋、トムは横浜港に降り立った。傍らには、半年前に結婚した妻・エマがいた。
トムは毎朝日本語の勉強を日課とし、東京、大阪など大都市から九州の各地に赴任。多くの独立自給教会設立に尽くす。
西南戦争で負傷した兵士や、板垣退助の要請で自由民権運動の志士たちにキリスト教の教えを説き、明治学院大学、東京女子大学、同志社大学、女子学院など、今日まで続く日本の高等教育を支えた学校の設立に携った。迫害、病気、貧困に直面しながらも、多くの人びとの命にふれ影響を与え、療養先のハワイで52歳で亡くなった。
そのころの日本はイギリスと同盟を結び、世界の列強と肩を並べるほどのアジアの強国となっていた。
トムの生きた“明治という時代”とはどんな世界だったのだろうか――。
最年少、女性で初めてOECDのナンバーツーである事務次長を務めた著者の曽祖父の一代記。誰よりも日本を愛したアメリカ人の物語。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
38
未知の国である日本に結婚してすぐ宣教師として赴任するには若者ならではの無鉄砲さと行動力があったのだろう。明治という時代をキリスト教徒からの視点で見ると、西洋からの知識を採り入れたいという知識欲と明治政府が神道を推し進めたことで他の宗教への嫌悪感が相反する感情として発露するのが手に取るように感じられる。一方宣教師として日本で生き残るには英語教育という点で突破口を開き、一神教であるキリスト教へ帰依させる道を取らざるを得ない立場を弁えつつ家族を守り続けた物語であり、著者の執念で解き起こしたこの手記は一読に値する2019/02/21
AR読書記録
6
外国人から見た明治日本ということで、イザベラ・バードの紀行のように、庶民の生活から、いわば下からの目線で昔の日本が垣間見られるのかなと思ったら、わりと上の方からだった。上からだからこそ、キリスト教の受容の過程の政治的な背景とか、日本が諸外国とどう対峙していったかなどの歴史を俯瞰できたのは、よかったな。教会があると(主に建物目当てで)寄ってしまうほうだけど、あの宣教師が建てた、といった観点からも、巡れるようになるといいなと思ったりする。やっぱり偉業だものね。2018/11/26
Hidden
2
明治時代の宣教師の長女と次女が日本の墓地に埋葬されていて、今なお大阪南吹田教会と女子学院がそれぞれの墓を守っている。宣教師のひ孫にあたるジョアンナさんが、曽祖父の手記と親戚の記録を調べ、日本に足を運んで関係教会や大学で確認して書き上げた調査研究である。本書がどのように出来上がったのかの記録でもある。日本側の関係者が丁寧な対応で調査の手助けするいくつもの場面は、日本人同胞としてうれしく誇らしく思える。ひ孫が出版しなければ消えてしまった世代を超えた家族の人間ドラマ。曽祖父とひ孫のセットでおもしろい。2019/01/29
かーんたや
1
生活史や国際なんちゃらに関心ある人はどうぞ。あとがきに「日常生活の雰囲気を加える努力をした」とあるが、これが本書の売り。しっかし結構いい暮らししてたようで、キリスト教への反感というより聖職者階級や権威主義への反感もあったのではないかな?2018/11/24