内容説明
神経細胞同士の伝達をよくすれば,脳を上手に使うことができます.それには,どうすればよいのでしょう? 記憶障害や失語症の権威が,研究の歴史をひもときながら,脳の基本的な構造や記憶のしくみ,経験を積むことや体で覚えることの重要性,上手な休み方や体内時計との関わりなどを通して,わかりやすく解説します.
目次
目 次
はじめに
第1章 学びにかかわる脳
1・1 大脳皮質は分業体制
脳は大きく三つの部分からなる/ブロードマンの脳地図/言語にかかわる部位/ペンフィールドが調べた各部の役割/はっきりした役割、あいまいな役割
1・2 記憶にかかわる領域
大脳辺縁系/大脳基底核/小脳/前頭連合野
第2章 脳は育つ
2・1 記憶をつくっていく
脳が育つということ/記憶の三つの種類/エピソード記憶は海馬から/記憶を保持している場所は/意味記憶とエピソード記憶/感情の荷札/手続き記憶/手続き記憶には二種類ある/言語の遺伝子/口に出すことで記憶する/手続き記憶を維持する/記憶のはじまり
2・2 思考とワーキングメモリー
認識と思考とのちがい/ワーキングメモリー/ワーキングメモリーの上手な使い方/判断と評価と行動の関係/失敗して覚える
2・3 言語を獲得する
のどの構造/どうやって単語を知るか/単語から文へ/文をつくる脳のしくみ/日本人の読み書き能力/ネアンデルタール人はなぜ進歩しなかったのか/言語をもったから進歩した
第3章 脳は可塑的である
3・1 失語症から回復する
脳が可塑的であるということ/他の場所が役割を肩代わりする/ブローカ失語/ウェルニッケ失語/肩代わり機能がはたらく
3・2 神経回路と可塑性
ニューロンとシナプス/回路が再生するのか?/シナプス効率が変化する/シナプスが消える
3・3 可塑性と学習との関係
可塑性研究のはじまり/カンデルの研究/塚原の研究
第4章 脳を育てる学び方
4・1 現場で学ぶ
脳を育てる学び方とは/貝の化石を採りに行く/体験学習/これも体験学習/フィールドワーク/答えのない問題こそおもしろい
4・2 表現活動をして、記憶を整理する
動物の絵と人間の絵/人間はいつから絵を描きはじめたか?/絵と言語/視覚障害者のイメージ/概念をつかむということ/語呂あわせで丸覚え/表現して連合記憶にする/表現すると、つぎの行動につながる
4・3 グループで学ぶ
先生の話を聞くだけでいいのか?/言語とグループ学習/チュートリアル学習/杉田玄白に学ぶ/部活動/ネット学習と批判能力
4・4 脳を休める
脳は発熱器官/体内時計/体内時計の上手な使い方/体内時計をまもる/上手に昼寝する/睡眠と脳のはたらき/寝つきをよくするには/夜遅くまでスマホはやらない/結びに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けいしゅう
乱読家 護る会支持!
Arick
takao
ああああ
-

- 電子書籍
- 君に愛されて痛かった【秋田書店版】(話…
-
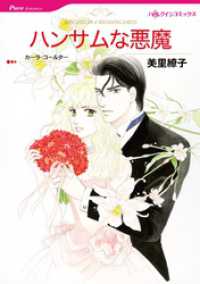
- 電子書籍
- ハンサムな悪魔【分冊】 8巻 ハーレク…
-
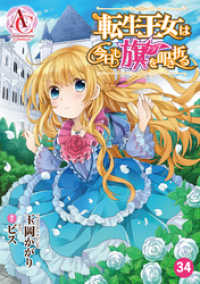
- 電子書籍
- 【分冊版】転生王女は今日も旗を叩き折る…
-
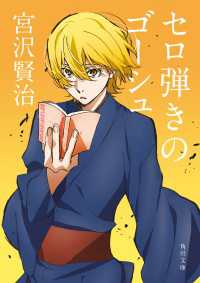
- 電子書籍
- セロ弾きのゴーシュ アニメカバー版 角…
-

- 電子書籍
- 酒と恋には酔って然るべき【分冊版】 2…




