- ホーム
- > 電子書籍
- > 絵本・児童書・YA・学習
内容説明
1918年6月1日、徳島県鳴門市の板東俘虜収容所……。ドイツ兵俘虜(捕虜)たちによって、ベートーベン交響曲「第九」が、アジアで初めて全曲演奏されました。初演の背景には、俘虜に対する人道的な配慮を行った松江豊寿所長の存在がありました。彼はドイツ兵俘虜に対して、「彼らも祖国のために戦ったのだから」と、俘虜の住環境の改善などについて上官に粘り強く交渉し、最後までその姿勢、信念を貫いたのです。後年、板東俘虜収容所の元俘虜であったパウル・クライ氏は、次のように言っています。「世界のどこに、バンドーのような収容所があったでしょうか。世界のどこに、マツエ大佐のような収容所所長がいたでしょうか」。なぜ、鳴門市では「第九」を皆歌うのか。……本書は、主人公の転校生・愛子が感じたこの素朴な疑問に、ドイツ兵俘虜の「私」が当時を振り返る形で答えます。日本初の「第九」演奏会から百年にあたる年の記念すべき発刊!
-
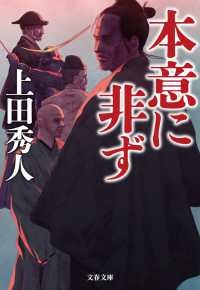
- 電子書籍
- 本意に非ず 文春文庫
-

- 電子書籍
- 見える子ちゃん 公式アンソロジーコミッ…
-
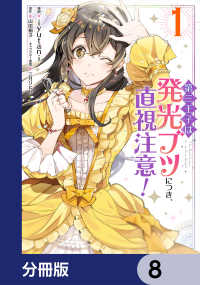
- 電子書籍
- 第三王子は発光ブツにつき、直視注意!【…
-
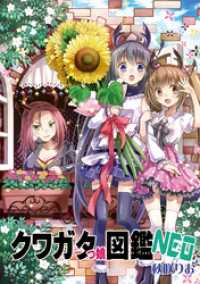
- 電子書籍
- クワガタっ娘図鑑NEO BLIC
-
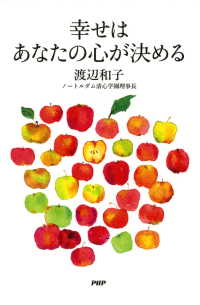
- 電子書籍
- 幸せはあなたの心が決める



