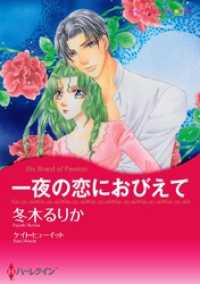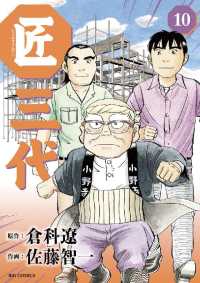内容説明
明治維新の混乱のなか起きた日本美術の海外への大量流出。そのとき海を渡った作品の中には国内に留まっていたら国宝間違いなしと言われるものも多数含まれていた。フェノロサやビゲローといった著名コレクター、エドワード・モース、フランク・ロイド・ライトのような意外な人物、そして林忠正や松方幸次郎ら日本人まで、当時の記録を丹念に読み解くことで外国人による日本美術買い付けの実態を明らかにするとともに、いまも続く美術品流出の是非を問う。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yutaro13
10
2012年に東京国立博物館140周年記念で開催されたボストン美術館展。長谷川等伯「龍虎図屏風」や曾我蕭白「雲龍図」など存在感溢れる作品は今でも目に焼きついてます。このときは仏像も多数展示されていたはずですが、今ほど仏像鑑賞趣味がなかったのであまり印象がないのが残念なところ。さて、日本にあれば国宝間違いなしともされる作品がなぜ海外にあるのか。様々な背景はあるものの、明治期に日本人が日本の芸術に価値を見出せていなかったのが要因のひとつのようです。若冲にせよ村上隆にせよ、そうした傾向は現代でも続いているのかも?2018/08/27
spica015
10
モースやフェノロサ等の手により海外へと渡った日本美術の至宝の数々。流出というと聞こえは悪いが、廃仏毀釈の憂き目から救い、日本人が忘れてしまった魅力に再度気付かせてくれる、という肯定的な面もある。学生時代に仏教美術を研究していたので、信仰対象として仏像や仏画がどのように扱われてきたのかは考えたが、美術作品としてどう蒐集・売買されてきたのかについては余り考えてこなかったので、興味深く読んだ。海外流出には、それに携わった人物の来歴が多いに反映されているが、割と私生活がダメな感じの人が多いのに苦笑いしてしまう。 2018/07/20
Wataru Hoshii
6
明治以降、国宝級の日本美術がいかにして海外に流出したのかを、モース、フェノロサ、ビゲロー、フリーア…といった著名な外国人コレクターたちの逸話と共に紹介する読み物。マイナスイメージで捉えられがちな美術品の流出だが、その時代の日本人が価値を認識できなかった例も多く、また流出したことで日本美術の世界的な評価が高まったという側面もある、という指摘に頷く。それにしても、アートはやはり経済と強くリンクしていると改めて思う。マネーのあるところに美術品が集まるのだ。海外の美術館にある日本美術を改めて見に行きたくなる一冊。2018/08/22
kri
5
宗達の「松島図屏風」がアメリカの美術館所蔵で原物を観る機会がないのが残念で、何故アメリカに?と思っていた。この本で詳細がわかってスッキリした。明治期〜日本に来た外国人=大森貝塚発見者モース、東京美術学校設立に携わったフェノロサ、ビゲロー、鉄道王フリーア、果てはフランク・ロイド・ライト等が次々と日本美術に魅了され買い漁っていく。時にはアンビリーバボーな安値で。経済的余裕もなく、グローバルな観点からの自国のお宝の価値に気付かず…仕方なかったのだろう。各愛好家たちの数奇な人生や日本美術への入れ込みぶりは興味深い2018/10/05
SK
4
結論が、経済力の重要性を強調するとは、身も蓋もないというか…。2021/08/21