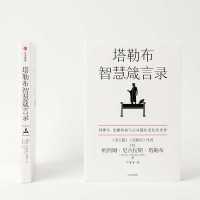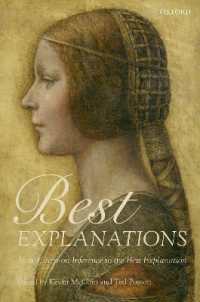内容説明
研究と学びの新たなる地平!「知」は個人の中に内在するため、その文脈の中で語られてこそ本質を理解することができる。すなわち「一人称」が研究のスタートとなる。これを積み上げることで「知」の攻略につなげられると考える。本書はこの一人称研究の考え方と実際の研究事例を丁寧な語り口で解き明かす。人工知能に興味のある読者、新たな研究姿勢を模索する理工学、人文系の読者も興味を持って読むことができる。
目次
第一部 知のどんな姿を明らかにしたいか?
第一章 一人称研究だからこそ見出せる知の本質
第二章 突き抜ける人の思考―羽生善治氏の将棋観
第三章 ことばを創造する知― 一度限りの感性
第四章 健康を育む知―高齢者の会話
第二部 どのように知の研究をしたいか?
第五章 研究という営みを自省する
第六章 知をデザインする
第七章 客観至上主義を疑ってみる
第八章 知の研究のスペクトラムを拡げる―人工知能研究の方法
第三部 一人称にまつわるQ&A
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やまもと
4
デザイン思考から一歩踏み込んで自分の身体知でユーザーと向き合う新しい手法と読み替えて読むと良い。ポイントはフィールドワークに置いて自分の頭にある知識で解釈をするのでなく、身体知で解釈をするということ。2018/11/01
すし
1
松尾豊「競争環境に於ては、自分の興味に従って研究をするという行動原理自体は全く強みにならない。競争環境と行動原理が合っているかどうか。」研究についての矛盾が言葉でわかりやすく説明されている。2016/07/08
鏡裕之
1
知能研究についての本。できるだけ多くのデータを取って、そこから普遍性を抽出していくのが、今までの研究。周りから「客観的」と言われるために、そうやって武装していたわけね。ある意味「三人称」的研究と言える。本書で紹介されている一人称研究とは、たった1人のデータを取って、有用なデータ(普遍性)を探っていくもの。多数という平均からは見えないもの、1人という突出したものからこそ見えるものを拾っていくアプローチ。ある意味、現象学的還元?(笑) 個人的には、非常にいいアプローチだと思う。2016/03/27
andaseizouki
1
自然科学の研究は、三人称視点で理論を構築するのが当然であり、客観性がなければ、論文にもならないのが事実である。しかし、人工知能や生体についての研究というのは、ある意味主観的な興味から始まり、一人称視点での研究になることもあるとは思う。これからの知能分野における新たな研究視点の可能性を書いた本で、面白さを感じた。2015/06/28
きよさん
0
読み応えのある本だった。「夜の研究」は楽しいよねー。2022/08/29
-

- 電子書籍
- リフレイム(分冊版) 【第10話】 ぶ…