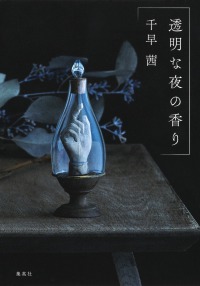内容説明
2018年4月、小中学校で「道徳」が「特別の教科」化され、児童生徒の評価対象に加えられることになった。
しかし、そもそも日本人にとって「道徳」とは何だろうか? この問いに答えられる親や教師はいるのか。
なぜ「学校」に通わなければならないのか?
なぜ「合理的」でなければならないのか?
なぜ「やりたいことをやりたいように」やってはダメなのか?
なぜ「ならぬことはならぬ」のか?
なぜ「市民は国家のために死ななければならない」のか?
なぜ「誰もが市民でもあり、奴隷でもある」のか?
なぜ「学校は社会に対して閉じられるべき」なのか?
そもそも「人格」「自由」「民主主義」「国家」とは何だろうか?
こうした基本的な問いをマクラに、ポップなイラストを織り交ぜながら、まず道徳の前提となる「近代」とは何かというごく基本的な意味から説き起こしていく。
ベースとするのはデカルト、カントの人間観と道徳観、ホッブズ、ロック、ルソーの国家観と市民観。
さらに中江兆民やレジス・ドゥブレなど、共和主義やリベラリズムの伝統もふまえながら近代的人間としての「道徳」と「市民」および「国民」としての「道徳」の原理を解説していく。
大人たちが最低限知っておくべき前提から問い直す一冊。
目次
はじめに
第1章 なぜ「学校」に通わなければならないのか―「近代」の意味から考える「学校」の存在理由
第2章 なぜ「合理的」でなければならないのか―啓蒙主義から考える「科学」と「道徳」
第3章 なぜ「やりたいことをやりたいようにやる」のはダメなのか―デカルトから考える「自由」と「道徳」
第4章 なぜ「ならぬことはならぬ」のか―カントから考える「人格の完成」
第5章 なぜ「市民は国家のために死ななければならない」のか―社会契約論から考える「国家」と「市民」
第6章 なぜ「誰もが市民でもあり、奴隷でもある」のか―ルソーから考える「市民」の徳
第7章 なぜ「学校は社会に対して閉じられるべき」なのか―共和主義から考える「士民」の徳
あとがき
さらに考えたい人のための参考文献 10選
その他のおもな参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
獺祭魚の食客@鯨鯢
sayan
樋口佳之
trazom
おせきはん