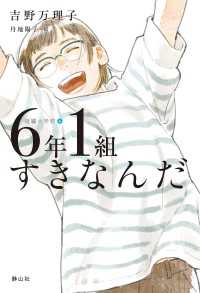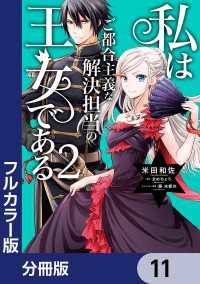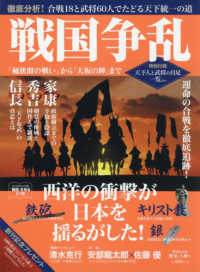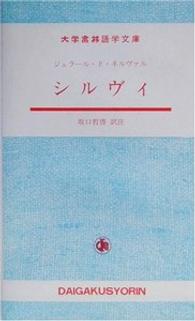内容説明
1930年代、社会システムの不調は盧溝橋事件発生へと至った。目的なきまま拡大する戦いの中、兵士たちは国家改造を期し、労働者や農民、女性は、自立と地位向上の可能性を戦争に見い出す。大政翼賛会の誕生はその帰結であった。前線の現実と苦悩、社会底辺の希望を、政治はいかにうけとめ、戦争が展開したか。統計資料から雑誌まで多彩な史料で当時日本の実像を浮かび上がらせ、日中戦争とは何だったのかを問う、著者渾身の一冊。(講談社撰書メチエ『日中戦争下の日本』改題)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
12
日中戦争について戦争指導者ではなく、労働者や小作人、女性などに着目して記述。内政における全体主義-自由主義、外交における地域主義-国際協調という軸で見ることで、近衛、東条、石原、昭和研究会、日本主義者、京都学派などそれぞれの目指した社会像がよくわかった。戦前から戦中に至る日本を単純化して捉えるのは危険。2020/10/22
かに
6
日中戦争初期、前線の活躍により銃後の人々も熱狂する。しかし、戦争が続くにつれて慰問袋の数の減少などからもわかるように熱狂も次第に冷めていく。軍需景気に国内は湧き、前線の兵の苦労に頭が回らなくなる中、帰還兵達はその状況に悲しみを覚える。 そんな中、国内では、労働者や農民が地位向上に向けて戦争を契機にデモクラシーを進展させていく。政党も政権獲得に向け、その流れに乗っていく。それがのちの大政翼賛会の結成に繋がり、日本の全体主義化へと向かっていく。2022/11/09
東京には空がないというけれど・・・
6
この本は、日中戦争の経緯や年次ごとの事件を解説したものではない。日中戦争から日米開戦、そして敗戦に向かう中で、農民や労働者という貧しい下層階級の人たちが、自らの差別を克服し、地位向上のために、「戦争」(正確には戦時体制による社会改革)を支持していたという視点で書かれたものである。上層にあるものと下層にあるものの平準化が、戦争、戦時体制においては実現できるとした運動について解説されている。さらに、現代における格差社会との関係性についても分析されている。全てに賛同するものではないが、極めて勉強になった。2020/08/27
hatohebi
5
中島敦の一高時代からの親友・釘本久春は、日中戦争に召集され、一年弱の戦地体験を経て文部官僚となり、日本軍占領地における日本語教育のイデオローグとなった。彼の斡旋で中島はミクロネシアへ赴き、後に南洋物を執筆する。最初の全集編纂者にも名を連ねるなど、大きな影響を与えた。「山月記」の袁傪のモデルとも目される人物である。本書は、兵士としての彼の日中戦争体験を考える上で、大変参考になった。「前線と銃後」という副題があるが、主に日中戦争下の国内社会の動きを中心に辿ったものである。「国民の戦争協力は、国家が強制したの→2022/09/06
刳森伸一
5
太平洋戦争ではなく日中戦争に注目し、その前線と銃後の関係から日本国内の変容を概観する。独特な歴史感だと思うが、読ませる内容だと思う。ただ、当時の人たちを少し美化しているようにも感じる(もちろん戦前礼賛系トンデモ本ではない)。2019/06/30