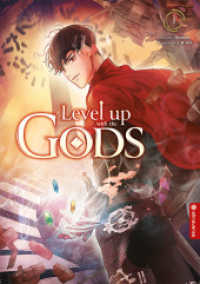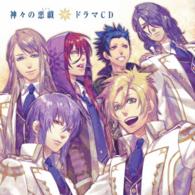内容説明
ヨーロッパ的な意味での個人の自由がないことを、中国のマイナス荷とみなすことは正しくない。
むしろ「公」「大同」や「縁」のつながりの中での利他の道徳性に、中国的な個の基盤がある。
そこに改めて注意を向ける必要がある。
ヨーロッパにあるものが中国にない代りに、
ヨーロッパにないものが中国にあるのである。(本文より)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゐ氏/きたの
0
中国の思想の根本概念である「天」「理」「公」を中心に解説し、その後の宋学の発展や辛亥革命の思想的根拠などについて説明した本。放送大学放映の話をまとめた本らしく、わかりやすく、所々で日本の思想との比較もありとても興味深かい内容であった。特に、中国の「天」と「公」の概念は日本の「てん」や「おおやけ」とは似て異なる概念で、万物の万民への平等・均等な配分を最もの理想とする中国の伝統的な考え方は今後の中国理解や日中思想史理解のヒントになるのではないかと思った。2016/02/17
kotsarf8
0
中国思想の概説本だが日本思想の勉強にもなる。同じ文字(漢字)を使っているということでさらっと流してしまう「理」「天」「公」など政治思想上も重要な概念が、日中の間で如何に異なった使われ方をしてきたのかが分かる。2012/03/24
ちあき
0
放送大学のテキストをもとに編まれた叢書の一冊。前半は「理」「天」などの基本概念に焦点を当てた日中比較思想史的記述、後半は宋学以降の思想を時代順に追っていくという構成。明清時代の社会に関する基礎知識があればすんなり読めるし、内容がスッと入ってこなければ高校の教科書・教材で確認すればよい、という意味で中国思想史の勉強にはもってこいの本。まえがきで「世に問う」エモーションをビンビン感じたので、結語に若干の物足りなさを否めなかったけれども、この値段このページ数に多くを望みすぎてはいけないのかも。2011/07/05
非実在の構想
0
前半は「天」「理」「自然」「公」という単語が中国と日本では意味内容が異なり、それが無自覚のまま受容されたことを指摘。後半では朱子学、陽明学がどのような背景をもって登場し変容していったか、また民末から現代に至るまでの状況の変化により思想がいかに変わり変わらなかったのかを述べる。 特に「理」が日本では主観と主観の相互関係における規範であり、中国における「理」が持つ普遍性・客観性を有していないため、朱子本来の意図とは異なるように読まれ古学派に批難されたという指摘に感激した。2018/06/24
-
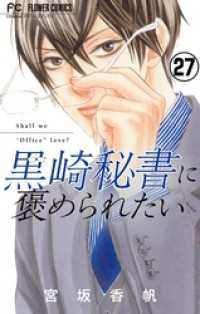
- 電子書籍
- 黒崎秘書に褒められたい【マイクロ】(2…
-

- 電子書籍
- 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリ…