内容説明
自律的な団体性を欠いた社会と、意思決定の集中化した巨大な政治的統合。これは専制国家の指標である。中国はいかにしてその体現者となり、今日に至ったのか。本書は、封建社会を通過して近代国家へと展開を遂げた日本との比較検討をふまえ、中国という国家の特質をつぶさに炙り出す。グローバル化の進展とともに社会の団体的結合原理が解体し、政治決定の集中化が急激に進行する現代にあって、中国のもつ歴史的様態は、はたしてどのような示唆を与えるのか──。多分野の成果を取り入れ、人類史的視野から国家像を描出した渾身の論考。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
11
メインは中国と日本との国家形成の比較だが、「中国史から世界史へ」という副題通り西欧の古典古代が参照されたり、話がボノボまで遡ったりする。日本が中国の後追い国家として数百年単位で発展に要する期間を圧縮させた点、日本も中国も戦国時代が社会再編の時代となったこと、そして中国共産党の支配について「社会は一見すると高い操作性を示した」としつつも、「しかし、政策を受け入れ、自ら具体化すべき自律的社会の無いがゆえに、政策は安定的に実質化されなかった」とする評価が印象的。2018/02/18
261bei
4
中国は開放的・流動的な「社会」であり、市場取引は常に零細化の圧力がかかり、取引コストは高止まりする。自律的・自治的な社会団体も成立しにくい。それゆえに専制国家による強圧的統治が試みられるが、その社会把握能力は低い。その問題点がとことん露呈したのが近代化の段階で、自治的な村落共同体の能力を活用できなかった中国では、たとえば土地台帳の作成に大変苦労することになる。他方、公共政策の担い手として重要なのが任意団体(様々な慈善団体)だが、これらも流動的組織であることに変わりはなく、下手をすると軍閥化する。2025/05/26
スプリント
4
古代から現代に至る中国と日本の国家形勢の比較論です。2018/03/31
どうろじ
3
「絶対的な真実も神も無いこの功利主義的な世界では、他者は手段化される。そこでは人格は早熟的に物象化される。」 世界史をヒトの統合の高度化と分業の構造化の過程であると仮定した上で、合議による合意への服従という規範の欠いた専制を前提とする社会が近代資本主義にどう影響されたかを論ずる内容でとてもおもしろい。今後は中国史にも目を向けようかと思う。2019/11/16
Yanagi
2
中国社会・政治の特質を「専制国家」と捉え、サルからの社会集団形成から古代帝国、そして現代中国までを、日本の封建的ムラ社会などと比較させながら論じた大変な名著。なぜ共産主義、党国体制が中国で根付いたのかずっと不思議だったが、共同体の不在など筆者の論点に鑑みると合点がいく。2018年、習近平はまさに現代における「皇帝」のごとき存在となった。それは中国社会の要請なのか(統治のために皇帝にならざるを得ないのか)、そうではないのか、その考察の一助にもなりそう。2018/04/15
-
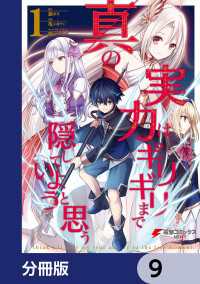
- 電子書籍
- 真の実力はギリギリまで隠していようと思…
-
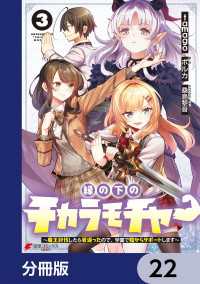
- 電子書籍
- 縁の下のチカラモチャー【分冊版】 22…
-
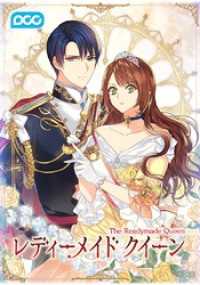
- 電子書籍
- 62話【タテヨミ】
-

- 電子書籍
- ブラックホール宇宙物理の基礎
-
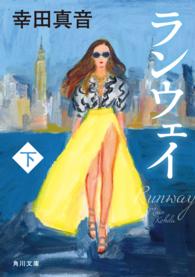
- 電子書籍
- ランウェイ 〈下〉 角川文庫




