- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
グローバル・スタンダードに沿おうとする構造改革路線が続く中、日本人は権威に弱く、同調主義的であるとの見方が強まっている。だが、本来、日本人は自律性、主体性を重んじてきた。現在、改革をすればするほど閉塞感が増すという一種の自己矛盾の状態が続いているが、文化と伝統のある社会で日本人が持ち合わせてきた自律性と道徳観について、『菊と刀』や『リング』『貞子』『水戸黄門』なども題材にしながら論考していく。さらに、人々がよりいきいきと暮らせる安定した社会を取り戻すためには何が必要か、真っ当な国づくりについても考察していく。気鋭の政治学者で、話題作『英語化は愚民化』著者による画期的日本論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こも 旧柏バカ一代
25
日本人は他人を見て行動する。日本の怪談は因果応報なタイプが多く、悪い事をすると被害者から報復を受ける。キリスト教文化圏は自己主張する文化で、自身の意思を優先する。怪談では法律を破った者が、神からの裁きを受けて苦む物が多い。第二次産業主体の時代では他人の目を気にする日本人の特徴は合致し発展したが、1990年代辺りから齟齬が出て来た。構造改革を断行しようとしたがどうもシックリ来ない。だって参考にしているのはキリスト教文化の法律重視の改革で日本人には合ってないようだ。日本は独自の改革を開発するしかないらしい。2020/06/03
hk
24
「日本には封建的なものがいたるところに残っているため、市民社会の熟成が阻害されている。そしてバブル以降の経済停滞は封建的な日本型経営慣行などが原因だ。だから経済成長路線にもどすために”構造改革”をなさねばならぬ」 と1990年代中葉から経済や教育現場において鳴り物入りで開始されたのが構造改革だ。しかし構造改革をすればするほど日本経済は低迷し、世の中には閉塞感が広がっていく… 本書はこの悪循環の要因を「そもそも日本人は自律性や主体性がなく、流されやすいのか?」というラディカルな問いに立ち返って論考している。2018/09/20
Tatsuya9
13
長年、無意識的に抱いてきた疑問を払拭してくれた良書。日本人には、欧米とは違う自律を確立する形がある。ベネディクトの「恥の文化」という捉え方は一面的であり、的を得ておらず適当ではない。民話や怪談、国語の教科書からも文化の違いが垣間見える。▼グローバル化(実質は欧米化)の名の下に行われる構造改革は表面的であり、日本人の中で無意識に根付いたものとは違うものであるため馴染まない。▼かなり勉強になった。施光恒氏は『英語化は愚民化』でも感じたが、鋭い指摘が多く、日本が辿るべき道の本質を捉えている学者の1人だろう。2020/03/29
父さん坊や@FIRE
12
これは良書と言える。著者の渾身の思索から来たものだ。ただし彼の言うことは一応の首肯ができるものだが、それを実行に移すにはリスクがある。日本社会の土台を為す権利や契約、近代的な概念まで突き崩そうという動きに繋がりかねず、無責任な議論を促しかねない。そうは言っても西洋の衝撃をいかに受け止め直すか、何度か読み直したくなる本だ。2018/12/09
ふたば
11
日本と欧米の「自律的」には大きな違いがある。日本の自律性は、他国のモノとはかけ離れている。日本人は他者との関係性で、欧米は自分視点から、自分の立ち位置を決定する。戦後、欧米は日本の文化にその非を見出し、日本のメディアや識者(の一部)がそれに乗っかってしまった。日本的なものがどんどん否定され、日本人は欧米の生活様式や、考え方を取り入れようとした。そして、日本は日本らしさを捨てようと躍起になっている。本書は日本人がグローバル化の名のもとに、失おうとしているナショナリティをもう一度取り戻すことを提案している。2018/11/19
-

- 電子書籍
- 害悪姉と決別します【タテヨミ】 第72…
-
- 洋書
- Works
-
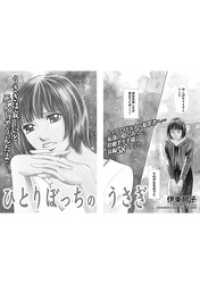
- 電子書籍
- ブラック主婦 vol.2~ひとりぼっち…
-

- 電子書籍
- INVESTOR-Z (11) コルク
-

- 電子書籍
- DOGS / BULLETS & CA…





