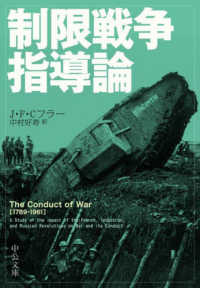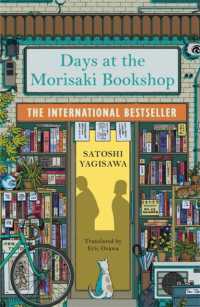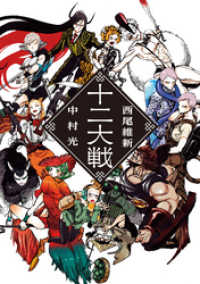内容説明
互いに引かれあうトランプとプーチンの真意、中国「一帯一路」の最終形、弱小国・北朝鮮が求めるもの、移民と難民に悩む欧州と中東……そして日本の行く先は? 隘路に嵌った資本経済と民主主義から生まれる人々の「怒り」をキーワードに、エゴを剥き出しに動き始めた国々の“行動原則”と世界を見るための“8つの指標”を示す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
8
国際情勢を「地政学」と「怒り」を切り口として纏めた本です。ただしリベラル寄りの分析をしているため、理念や理想を重視するのはいいのですが、支持している国や人物には甘く、そうでない国や人物には辛い評価を下しているので、その部分は割り引いて読む必要があります。また、「怒り」についても表層的な分析に終始しているので、「怒り」の原因が本当はどこから来ているのかが見えにくくなっています。日本は米中両国と良好な関係を築くべきだと述べていますが、米中貿易戦争が起きている現状を見れば現実的な見解とは言えません。2019/01/11
Meistersinger
4
地政学というか、昨今の国際情勢のおさらい本。地政学についてマッキンダーあたりから纏めている。具体的な個別事例を「怒り」(これはドミニク・モイジの影響だろう)で説明している。2018/02/16
templecity
3
難民問題、宗教対立、トランプ政権誕生などで世界が益々内向きになっている。そのような中で地政学的考えが重要となってくる。日本は中国、韓国と必ずしも思想が一致していない国と隣接しており、地政学的には不利な場所に位置している。更に経済的な重要度が相対的に低下していることから、米国などの関係が重要となってくる。2018/05/01
お抹茶
2
トランプ政権がやったように,自由で開かれた国際秩序の覇者であった米国が秩序を捨て去ることは,むき出しのパワーを競い合う地政学の時代に突入する。読みながら,ポスト・グローバル時代とポスト・トゥルース時代は理論的に重なり合うのかなと思った。2020/11/21
yuji
2
この本を読んで「忘れられた人」の怒りが火種になることがよくわかった。グローバリズムの胡散臭さは感じていた。インターネットの普及でいち早く国境を越えたのが金融業であった。資本があればあるほど不労所得が増える仕組みで、国境を越えられない人、技能がない人は忘れられていく。今日より明日はより良くなっていくのも胡散臭さ。未来を先食いしているだけで後生の人に負の遺産を残すだけだ。民主政はポピュリズムにより衆愚政になる。権威のある人に導いて欲しい思いが独裁者に付け入られる。古代ローマの共和政は王者の集まりの如くだった。2019/03/28