内容説明
「食べられるもの 食べられないもの」を理解して、訪日外国人のおもてなしに備えよう!多文化共生時代に必要なムスリム(イスラーム教徒)対応の実用書。ハラールとはイスラーム法によって許された物事をいう。飲食物のハラールの基礎と、いろいろな課題をおさえて、認証に頼らないムスリム対応の具体的な対策を提案。
目次
序 章 認証に頼らないムスリム対応とは
1.ムスリム市場とハラールビジネス
2.インドネシアから日本へ:ハラール研究とのかかわり
第1章 ハラールとは何か
1.イスラームの基礎
2.ハラールの基礎とその根拠
3.ハラールとハラームの原則
4.不浄と浄め
第2章 ハラールビジネスとハラール認証
1.ハラール肉と屠畜証明
2.ハラール認証制度
3.ハラールはハラール認証より広い
4.日本の食品産業とハラール認証
5.インバウンド・ビジネスと各種の認証
第3章 ハラールとハラームの狭間で
1.ムスリム消費者の意識の多様性とその要因
2.シーフード
3.肉の諸問題
4.「疑わしいもの」の拡大と風評
5.アルコール:ハムルをどこまで認めるか
第4章 ムスリム観光客の受け入れに向けた飲食サービス
1.試行錯誤で対応していく
2.すぐにできること:表示の工夫
3.一歩進んだ対応:場所・器具をわける
4.もう一歩進んだ対応:食材のハラール化
5.いちばん大事なこと:ムスリムの声を聞く
付録1 礼拝への対応
付録2 断食への対応
付録3 ハラール食材の入手方法と情報サイト
-

- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版 2024年 1…
-
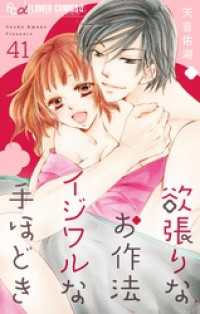
- 電子書籍
- 欲張りなお作法 イジワルな手ほどき【マ…
-
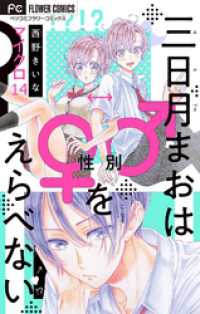
- 電子書籍
- 三日月まおは♂♀をえらべない【マイクロ…
-
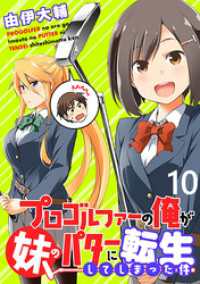
- 電子書籍
- プロゴルファーの俺が妹のパターに転生し…
-
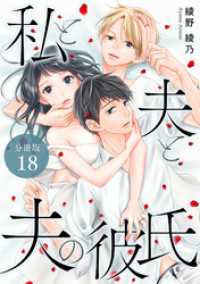
- 電子書籍
- 私と夫と夫の彼氏 分冊版 18巻 ゼノ…



