- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
現在の学校教育は一斉指導のスタイルである。教師は一人一人の個性を把握できておらず、子どもの抱える課題も見抜けない。もはや教師だけに任せられない現状を打開する唯一の解決策、それが「教育ケア」という考え方だ。「看護」の概念を取り入れ、医療と教育の協働を推進する「教育ケア」は、子どもの異常を発見し、個性を伸ばす。混迷する学校をも救う画期的な一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
oooともろー
2
「学校教育の限界」とは?キリスト教的な内容を省いても「ケア」の視点・対話・潜在力など、普遍性はある。著者も述べている通り、現政権の教育観・道徳観とは真逆。2019/03/04
セシリア
2
ナイチンゲールの看護についての哲学を基本に展開する教育論。スタートラインが「神」を前提としている為、ここに立てない人にとっては読んでも辛いのではないか。「学校教育の限界」は確かにあると賛同するが、なかなか筆者のようにはいかないのが現状だと思う。2018/05/07
Shun
1
ええと、結局著者の言いたい「学校教育の限界」とはなんだったのだろう・・・。要は著者の実践してきたナイチンゲールの看護を「教育ケア」という形で学校教育に活かせないか、という話だったのかな。とにかく論点があっちこっち飛ぶ上、このタイトルなのに序盤50ページくらいナイチンゲールがどういう人物か突然説明されて「何これ?」と思ったし、ハッキリとした話の導入に失敗しているような印象しか持てなかった。2019/01/30
さるたん
0
今の学校教育には限界があり、子供の全人的ケアの概念に基づき、周囲の様々な職種の人々が、子供に対して真に興味を持ちながら教育に向き合っていくべきである。 これが主張の大部分のように思いました。 ただ、キリスト教的な価値観を持っていないとなかなか受容しづらい部分が多くあるように感じます。(相当な「性善説」に近い考え方だなあ、それって本当にどうやったら実現できるの?と思ってしまったので…) あとは論点がどんどん飛ぶので一気に外観を掴む読み方をした方が良さそうです2019/06/20
-

- 電子書籍
- 転生魔女は運命の王子を見つけ出してしあ…
-
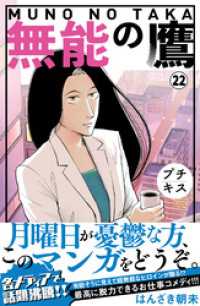
- 電子書籍
- 無能の鷹 プチキス(22)
-
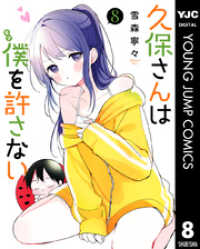
- 電子書籍
- 久保さんは僕を許さない 8 ヤングジャ…
-

- 電子書籍
- 恋は妄毒(3)
-
![iPhoneユーザのためのMac活用テクニック [同期・連係・共有] - iPhoneとMacを一緒に使えば、もっと簡単、便利に! Mac Fan Special](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0581483.jpg)
- 電子書籍
- iPhoneユーザのためのMac活用テ…




