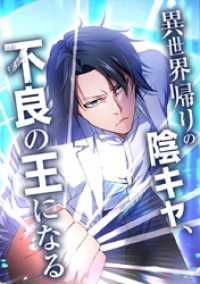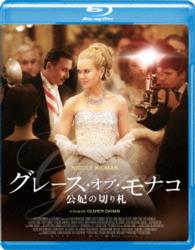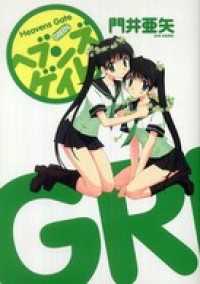- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
信長の「能力主義」はどこからきたのか? それは、父・信秀から引き継いだ体制に理由があった。有力部将の多くは従属的ではなく、代々仕える譜代家臣が少なかった。そのため、重臣には戦闘動員力を持つ国人領主をあてざるをえなかった。能力や資質よりも門閥主義を選択したが、徐々に小身の側近たちを抜擢していった。信長が、自らの家臣団をどのようにして最強の軍団へと成長させていったのか、豊富な史料を使って検証する。
【目次】
第1章 前史としての父・信秀
1 信秀の擡頭
2 那古野城攻略
3 三河攻略
4 美濃出兵
第2章 信長の尾張統一
1 信秀の死
2 清須織田家との対立
3 筆頭家老・林佐渡守との対立
4 尾張の統一
第3章 桶狭間の合戦と美濃・近江侵攻
1 桶狭間の合戦(永禄三年五月)
2 美濃侵攻
3 足利義昭を奉じて上洛
第4章 織田家臣団の形成
1 信秀家臣団はあったのか
2 青年期・信長の部将は家柄で選ばれた
3 カネで買った旗本を育てる
4 旗本から部将への昇格
第5章 方面軍ができるまで
1 近江 有力部将による分封支配
2 近畿 旧勢力の温存
3 越前 方面軍司令官の誕生
4 近江の直轄化と家督譲渡
第6章 方面軍司令官の時代
1 方面軍司令官とは
2 柴田勝家(天正三年九月)
3 佐久間信盛(天正四年五月)
4 羽柴秀吉(天正五年一〇月)
5 瀧川一益(天正一〇年四月)
6 神戸信孝(天正一〇年六月)
7 織田家臣団としての明智家臣団
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鐵太郎
22
著者は「徳川家臣団の謎」という本を先に出していたとのことだけど、こちらが目にとまりました。研究が進んでいる信長の生涯、戦い、家臣団について、新たにまとめ直したものと考えればいいのかな。前史として父・信忠からはじめ、信長の勢力拡大から「方面軍」、そして本能寺まで。織田家は実力主義という「定説」に対し、それだけじゃない、「家柄」「地元の有力者」の登用が意外に多いよ、というところが斬新かな。地図や系図や一覧表が多く、見やすくする工夫が見られます。(でも地図はもうひと工夫ほしいものがあったなぁ)2025/09/19
bapaksejahtera
15
信長の人材登用は家柄に捕らわれぬ実力主義だと通念されるが、案外に門閥や国人層への配慮に厚かった事を実例を以て記述。信長の直系が多くの織田系統の中の一分派に過ぎず、元々譜代の家臣に乏しい中で尾張の統一果たした事。その過程では中世的な守護や守護代の権威を利用しなければならなかった事を述べる。又尾張南部の経済的利点を活用し有力武士次三男を庸雇するのも目覚ましい。桶狭間合戦等を経て勢力を拡大する中、広域を有力武将に方面軍的に委ねる方式を取るが、それに当る秀吉勝家光秀等の家臣団構成についても同様に遺漏なく説明する。2023/10/26
餅屋
4
織田家臣団のまとめ本です。父信秀の台頭期から説明しています。最近の学説を取り入れ、信長は保守的であり、実力主義的な人材登用をしていたわけではなく、家柄や動員能力で武将を選んだことを説明しています。時代ごとに、地図や家臣団の表が入っており、解りやすく便利です。桶狭間の合戦については、著者の新説を語っており、この説は小説などでも採用されていますね。(2018年)2021/05/10
ゲオルギオ・ハーン
3
よくある信長本かと思いきや信長の人事戦略に焦点を当てた面白い一冊。「信長の人事といえば実力主義」という先入観があるが、初期の頃は動員戦力の問題から能力を別にして動員力を第一に家臣を重用し、一方で将来を見据えて見込みがあり、既得権がほとんどない人物は育成枠として育てた。また、征服地が増えてくると既存の領主たちを下手にいじらず主だった家臣たちの下につけて彼らの領地経営がしやすいようにした。信長が勢力を伸ばしたのは既存の社会構造を利用しつつ先進的なアレンジをした人事戦略の妙技もあるのではないかと思いました。2019/09/07
Go Extreme
1
前史としての父・信秀 信長の尾張統一: 信秀の死 清須織田家との対立 筆頭家老・林佐渡守との対立 尾張の統一 桶狭間の合戦と美濃・近江侵攻: 桶狭間の合戦 美濃侵攻 足利義昭を奉じて上洛 織田家臣団の形成: 信秀家臣団は 青年期・信長の部将は家柄で選ぶ カネで買った旗本育成 旗本から部将への昇格 方面軍: 近江ー有力部将による分封支配 近畿ー旧勢力の温存 越前ー方面軍司令官の誕生 近江の直轄化と家督譲渡 方面軍司令官の時代: 柴田勝家 佐久間信盛 羽柴秀吉 瀧川一益 神戸信孝 織田家臣団としての明智家臣団2024/10/02