内容説明
天才は何がすごいのか? そんな素朴な疑問を、誰もが認める天才棋士・羽生善治をモデルに徹底解明。将棋との出会い、勉強法、対局で大切にしていることなど、本人が明かす驚愕の思考を最新科学がすっきり整理し、ついに能力の秘密が明らかになっていく。常に多くの決断を迫られる将棋だからこそ、その極意は人生の様々な局面にも生きてくるはず。向上心ある日本人のための画期的な一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こーた
142
天才を科学する。羽生さんの思考はアマチュア、それは将棋に限らずあらゆるアマチュアのことだが、大いにタメになるし、それを研究するサイエンスとしても十分に読みごたえがあった。書かれた当時は人間のほうが上だったが、いまや力関係は逆転し、将棋はおろか囲碁ですら、人間は機械に歯が立たなくなった。そんないま、羽生さんはどう考えているのか、あるいはほかの若い棋士たちや、なかでも現在のトップである藤井聡太は、機械とどう向き合っているのか、そんな「増補改訂版」なんかがあったら、読んでみたいな。2025/01/14
takaC
71
羽生さんとは残念ながら頭脳の性能が違うことを改めて認識した・・・2015/03/16
コウメ
56
将棋は2人でおこなうゲームであり、カードゲームのような相手の手札が見えないわけでなく、全て手は明かされている「完全情報」ゲームであり、サイコロのような不確定な要素を含まず「確定」ゲームである。ということはいかに情報を持っているかで勝負が決まる。「2人完全情報確定ゼロ和ゲーム」である。三目並べのような必勝も将棋には存在するがあまりにも複雑で人智をこえ、それを見つけだすのは不可能であるだから将棋様々なゲームと違って面白い。/うまくなれる練習というのはいかに長時間「考え続けること」これは新たな新手にも結びつく、2019/10/05
hope
34
★★★★ 某マグさんの将棋フェアに触発されて、積んでた本を漁ってみた。羽生氏が将棋観を語り、自ら治験者となって、人工頭脳と認知科学の専門家が解析、解説する。将棋本というより学術書の趣き。この本は2006年に出ているので、AIと将棋の関係などはかなり状況が変わっているが、十分面白い。 「発見と創造ーそれこそが私が将棋を指し続ける最大のモチベーションになっています」この羽生氏が放つ言葉の重みを、静かに嚙みしめる。2018/03/20
かおりんご
30
考える力って大事だと、改めて思わされました。教育者の端くれとして、子供たちにどうやって考える力を身に付けさせるのかが課題ですが、好きなことならじっくりと向き合って考えてくれるのでしょうが、授業の中になると難しい。算数の式をたてるだけではなく、図やグラフ、絵に表すことも考える力の育成には有効なようなので、続けていきたいと思いました。それにしても、羽生さんはすごい!2018/10/16
-

- 電子書籍
- レッツゴー!まいぜんシスターズ 全身が…
-

- 電子書籍
- ふりだしから始まる覚醒者【タテヨミ】第…
-
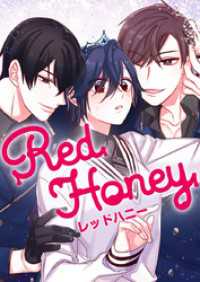
- 電子書籍
- Red Honey【タテヨミ】第34話…
-
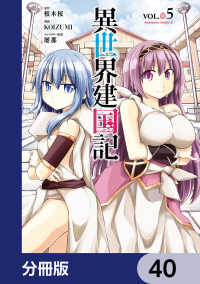
- 電子書籍
- 異世界建国記【分冊版】 40 角川コミ…





