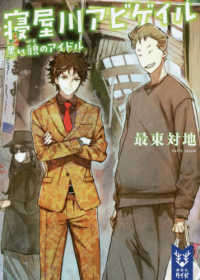- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
西洋だけでなく、インド、中国、マヤなどの天文学にも迫った画期的な天文学通史。神話から最新の宇宙物理までを、時間・空間ともに壮大なスケールで描き出す。人類は古来、天からのメッセージを何とか解読しようと、天文現象を観察。天文学は、地域や文化の壁を越えて発達し、政治や宗教とも深く関わってきた。本書は、天体を横軸に、歴史を縦軸に構成。学者たちの情熱、宇宙に関する驚きの事実や楽しい逸話も織り込んでいる。
目次
はじめに
第一章 太陽、月、地球――神話と現実が交差する世界
第二章 惑星――転回する太陽系の姿
第三章 星座と恒星――星を見上げて想うこと
第四章 流星、彗星、そして超新星――イレギュラーな天体たち
第五章 天の川、星雲星団、銀河――宇宙の地図を描く
第六章 時空を超える宇宙観
終章 「天文学」と「歴史」
謝辞
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
86
一章:太陽、月、地球 二章:惑星 三章:星座と恒星 四章:流星・彗星・超新星 五章:天の川、星雲星団、銀河 六章:時空を超える宇宙観 終章:「天文学」と「歴史」で構成されている。人といちばん身近な月や太陽では暦のことに触れている。いつも感じるのは暦で日々生活していることを考えると古代の人々の知見はとてもすごいものだということ。現代の精巧な望遠鏡がない時代に木星や土星、天王星、海王星を観察していたことなど他。またこの本に書かれていることを例えばプラネタリウムで解説などしてくれたらとてもいいなあ。2018/04/01
へくとぱすかる
64
天文学の歴史を、太陽・月から始めて、宇宙へ広げる形で述べているので、それぞれ分野別の簡素な研究史として読める。終章のいわゆる「インドの宇宙観」について、実際にはヨーロッパ人による誤解、もっといえば偏見から形成されたとは知らなかったし、千年前のイスラム世界の科学者が、驚くほど公平な見方をしていたことも、深く考えさせられた。色眼鏡で見てはいけないと。2019/02/17
HMax
23
面白い小ネタ満載。どうして週末の日曜がカレンダーでは週の初めなのか?閏年の閏という漢字の成り立ちは?日本では曜日と惑星の名前が一致しているけど、英語では異なるのはどうして?それにしても日本では肉眼で見える星の数が少なくて残念。年に一度、七夕の夜ぐらいは全国一斉に電灯を消すっていうのはどうでしょう。2018/03/30
読書好きのハシビロコウ
20
天文学の発展の歴史を天体単位で区切って追っていくのが特徴。そういう性質もあって世界史が好きな人にもとっつきやすい一冊となっています。古代には神聖なものとして恐れられ、崇められてきた天体たちが、技術が進歩するにつれ、神聖さよりもロマンの塊としての存在感を強めていくのはグッとくるものがあります。多くの研究者が編み出しできた説を追うのは少し疲れましたが天体を語源とする様々な言葉があるのには好奇心をくすぐられました。2025/01/05
びっぐすとん
18
再読。寝る前の睡眠薬として一週間かけて読んでいたが、後で書き出そうと栞を挟んでいたのに、寝落ちしてベッドから本を落とした弾みで挟んだ栞が全て本から外れてしまった。寝惚けた頭で挟んだ場所なんて、もう覚えてない・・・。1つだけ覚えているのは、元々1週間は土曜日から始まった。なので西暦1年1月1日は土曜日。イランから中央アジア、日本は太陽を重視していた為、日曜日始まり、西洋は日曜日を安息日とした為、月曜日始まりである、という部分だけ。今回2度目なのに新鮮な気持ちで読めたし、たぶん何度でも睡眠薬として使えそう。2020/06/21
-

- 電子書籍
- 悪役希望の骸骨魔術師 2 GCノベルズ
-
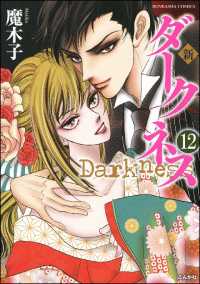
- 電子書籍
- 新 ダークネス(分冊版) 【第12話】