- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
杉浦康平はデザイン界の逸材と言われ、一貫して独創的な手法を切り拓いてきた。また、ウルム造形大学、インド旅行での経験から、アジアの伝統文化に目覚め、広くアジアの図像を探求し、曼荼羅のほか、余人の及ばない成果を展開している。
目次
第1章 建築を学んだ異才のデビュー-一九五〇?六〇年代初め
第2章 デザイン活動の本格化-一九六〇年代
第3章 転機となるウルムでの指導-一九六〇年代後半?七〇年代前半
第4章 アジアへの開眼とブックデザインの革新-一九七二?七六年
第5章 アジア図像学の集成へ-一九七七年?八〇年代
終章 アジア・デザイン言語共同体の軸に-一九九〇年代以降
-
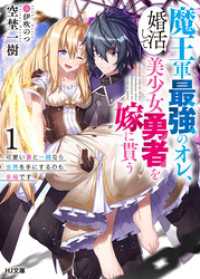
- 電子書籍
- 【電子版限定特典付き】魔王軍最強のオレ…
-
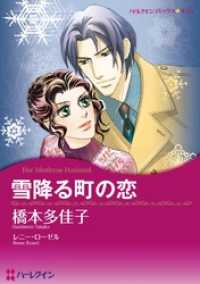
- 電子書籍
- 雪降る町の恋【分冊】 2巻 ハーレクイ…
-

- 電子書籍
- 世界で一番、俺が○○ 分冊版(28)
-
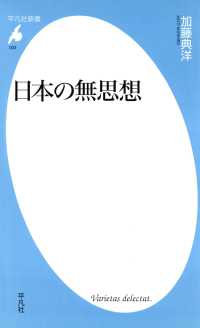
- 電子書籍
- 日本の無思想 平凡社新書
-

- 電子書籍
- ここまでわかった! 新選組の謎 新人物…



