- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
二十代、人工透析。三十代、腎臓移植。四十代、移植腎の不全・人工透析再開。五十代、腹膜透析。ルネサンス研究者である著者は、若くして腎臓を病み、以後肉体の理不尽に翻弄されつつ、いのちの再生を我がこととして、生きてきた。そこで直面した生と死、身と心のかたちとは?抽象的な「身体」でなく、生身の「肉体」を軸に、当事者の立場からいのちの倫理を考える。
目次
第1章 腎臓移植を受けた者として(臓器移植体験者として
移植された臓器が死んだ日 ほか)
第2章 透析・移植医療あれこれ(摘出されなかった移植腎
体験者無視の不毛さ ほか)
第3章 「からだ」を見つめて(肉体の仮称性-身心と心身
毀形-「異状」という「生」 ほか)
第4章 他者からの視線(身障者の保険加入を拒む「病歴」
理不尽、その正逆 ほか)
第5章 「いのち」に向き合う(仏教者の視点
「こころ」と向き合う ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うたまる
1
人工透析、腎臓移植を経験した著者の生命観と身体観についての考察。どいつもこいつも現場視点が欠けている、と著者は憤る。学者も医師も宗教家もだ。まあそりゃ、臨死体験者からすればそういう感想を抱くのも無理ないかもしれない。それならその体験者の見解を教えてもらおうじゃないの、と読んでみる。曰く「生命ではなくいのち」「身体ではなく肉体」「いかに生きるかではなくなぜ生きるか」ときた。はい、分かりません。さっぱりです。理解するには読解力よりもやはり実体験が必要なのか?尚、3章が最も難解だが、それ以外ならそこそこ頷ける。2017/02/12
-
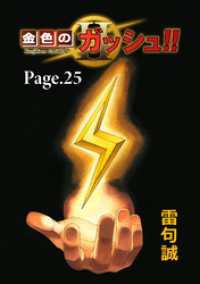
- 電子書籍
- 金色のガッシュ!! 2【単話版】 Pa…
-
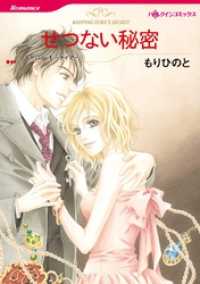
- 電子書籍
- せつない秘密【分冊】 9巻 ハーレクイ…
-

- 電子書籍
- 転生したら乙女ゲーの世界? いえ、魔術…
-
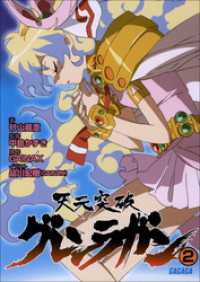
- 電子書籍
- 天元突破グレンラガン2 ガガガ文庫


![ゼロトラストネットワーク[実践]入門](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42971/4297126257.jpg)


