- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
鯖や塩などの海産物から醤油や唐辛子などの調味料まで、さまざまな食品・食材が伝わってきた道をたどり、日本の食文化の流れを俯瞰する。
目次
第1部 海辺から山への道(鯖街道-小浜から京都まで、ひと塩した鯖を背負って駆け抜けた道
ぶり街道-山国の正月の年取り魚=塩ぶりがたどった峠道 ほか)
第2部 海上の道(昆布の道-北海道から大阪へ。北前船で運ばれた和食の基本だし
醤油の道-紀伊半島から房総半島へ。醤油が下ってきた航路)
第3部 権力者がつくった街道(鮎鮨街道-鮎好きの歴代徳川将軍に届けた高速道
お茶壷道中-本場・宇治からひと夏かけて運ぶ新茶の道)
第4部 渡来食品が伝わった道(砂糖街道-長崎に始まるシュガーロードの甘味のすべて
豆腐の道-京豆腐は風雅をきわめ、江戸豆腐は庶民の人気おかず ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
45
多様な日本の食文化の背景には、この本に出てくる街道が大きく関係していることを知った。また食品を加工することにより保存性を高める工夫、先人たちはどうやってそのことを知ったのか。世界各国でみられる発酵食品について小泉武夫先生の著書を思い出した。2015/11/27
ようはん
18
若狭の鯖を京都まで運ぶルートの鯖街道は割と知られていて本書でも触れられているけど、他にも富山の氷見から飛騨方面や信州に鰤を運ぶ街道や鮑を焼津から山梨に運ぶ街道があったのは初めて知る。2022/11/29
ホークス
12
京と福井をつなぐ鯖街道をはじめ、ぶり街道、塩の道など全国の「食の街道」を訪ね、歴史や風土に触れながらその街道ならではの味をレポートする。味の継承・紹介に尽力する人達についての記述も多い。個人的には、一時仕事をしていた長崎を訪ねる「砂糖の道」の項を読んで、当時を懐かしく思い出した。ちゃんぽん文化やしっぽく料理によって、地域食の底知れない独自性に触れることができた。その後高松のうどん文化には驚異さえ覚え、この国には小さな食の王国が無数にあることを知った。そのことにささやかな救いを感じるのは私だけだろうか。2015/09/06
もけうに
4
魚・醤油といった歴史を感じるものから、さつま芋・唐辛子のような舶来物まで、日本の食街道は奥深い。詰まるところ伝統食も江戸時代起源が殆ど。お江戸小説好きとしては楽しい。京と江戸の食文化の違いも興味深い。保存技術・輸送手段が未発達な時代だからこそ生まれる美味もある。ユーモアの効いた文章で、クスッと笑えるところもあり楽しい。2021/11/22
ぷくらむくら
2
先人たちの想いを想像しながら一度この道を歩いてみたいな。2011/03/30
-

- 電子書籍
- 午後5時のメイド【タテヨミ】第23話 …
-
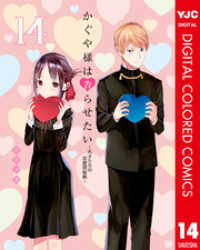
- 電子書籍
- かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭…
-
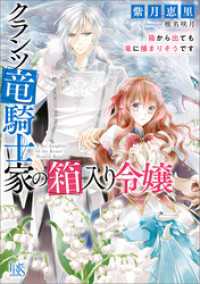
- 電子書籍
- クランツ竜騎士家の箱入り令嬢 箱から出…
-
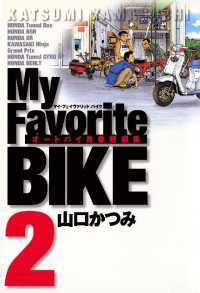
- 電子書籍
- My Favorite BIKE(2)…





